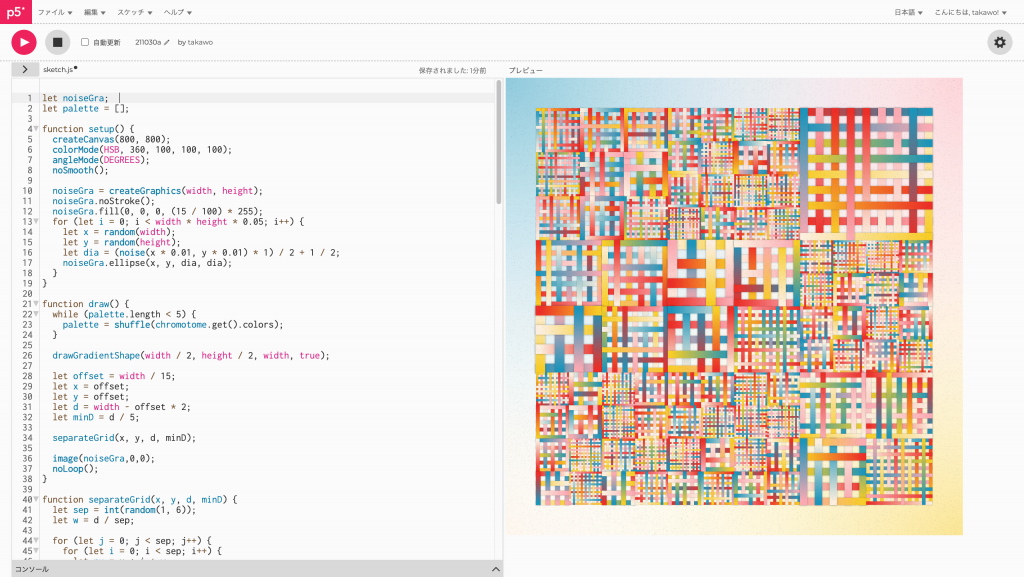作品になんらかのダメージや欠損が認められたとき、その原因を分析・特定し、復旧すること。あるいは、作品のより望ましい保存のために素材や構造を分析し、最適な保存・収蔵方法を導くこと。こうした役割を担う修復士は、作品における医者のような存在とも言われる。「患者」となった作品が蘇るために何が必要かを見極め、ときに直接手を加える責任の重みは計り知れない。
保存修復理論や保存修復史を専門とし、国内における数々の展覧会でコンサべーターを務めてきた田口かおりも、極微の世界で作品と向き合ってきた修復士のひとり。とくに現代アート以降は未知の素材や展示形式など、作品を取り巻く要素は多様化しており、近年では作品の「死」を認めようとする動きもみられる。本稿では、著作『保存修復の技法と思想: 古代芸術・ルネサンス絵画から現代アートまで』を足がかりに、現在における修復のあり方とそのゆくえを田口に伺った。
無我を理想とする修復論からの脱却
まず、なぜ田口さんが修復士を目指そうと思われたのか、その経緯を教えてください。
まだ子供だった頃、両親に連れられて行ったミラノの大聖堂を見て衝撃を受けたんです。人間はこんなすごいものを作り、しかもそれがこんなにも長い間残っているのか、と。これはなにも素材だけの問題ではなくて、イタリアには戦争や被災といった戦禍を乗り越え、いろいろな人の手が入ることで残り続けている建築物がたくさんあります。そういった多くの危機を乗り越えてきたモノを私は見ているのだと、とても感動しました。その体験から、将来自分自身も作品をあとの世代に遺していくための手伝いをしたいなと思ったのが一つです。
もう一つは、保存修復の道に進もうかと思いはじめていた頃に、フィレンツェの工房に見習いとして一ヶ月ほど入れていただいたときのこと。工房主に、修復家に一番必要なスキルは?と聞かれ「目がいいことでしょうか?」と答えると「大切なことは、どれだけ自分を消すことができるかだ」と言われたんです。
「美術史における作品の知名度や価値、自分の美意識に合うかどうか。そういった基準をすべて取り去って、目の前にあるものをただ見ること。さらにそれを『今以上の何か』とか『より綺麗なもの』にしたいという欲を消して、フラットに向き合うこと。そうして自らの価値基準や趣味をどれだけゼロに近づけられるかが、修復士になるために必要なトレーニングだ」と。
当時は20歳くらいで、生き方や職業に悩んでいた頃。周囲では就職活動が活発で、自分の個性や特性とは何か、自分にしかできないことはどこにあるのか、といった問いの言語化に四苦八苦する景色をよく目にしていました。そんな時に、「自分にしかできないこと」を極めるのではなく、むしろ「自分をどこまでも消すこと」を良しとする仕事が世の中に、しかも美術の世界にあると知って、人生の中でひと時でもいいから徹底的に自分を消す作業を試してみたいな、という好奇心が芽生えたんです。その二つが大きかったですね。
大学卒業後、イタリアに渡り修復技術を学ばれたとのことですが、修復士としてどの範囲を専門とされているのでしょうか?
私が通ったフィレンツェの学校では、フレスコ画、絵画、彫刻などのコースがあり、私は絵画科にいました。そのため、板絵の黄金テンペラ画などといった古い時代の作品を扱うことが多かったんですが、近代の作品を扱うこともあり、範囲は広かったです。
絵画の修復技術は色々な対象に応用できるので、貴族のお屋敷の扉を直したこともありましたね。メディチ家の末裔の別荘地の扉は彩色が綺麗で、それ自体が絵画や彫刻のように美しくデコラティブなんですけど、その補彩や剥離止め、洗浄、構造補強をしたり。絵画修復専攻は額縁の修復も習得する必要があって、額縁の欠損を部分的に補って彫ったり、箔を貼り直したり、多彩色の木製彫刻の修復をするトレーニングも行っていました。なので、厳密に何かの専門というよりは、絵画修復を総ざらいで学んで巣立つ、という感じでした。

普段、修復のお仕事はどのようにされているのでしょうか?
所属は大学ですが、客員修復士という形で「森絵画保存修復工房」という工房にも所属していて、ここが手を動かす主な修復の現場です。大学では研究と、必要な場合には光学分析などを行っています。たとえば作品の小さな剥落片から、レイヤーの構造や使用されている絵の具の種類を解析したり、ダメージの原因を科学的に特定するといった作業をしたり。場合によっては作品のCTを撮ったりもします。
どの作品を修復するかは主体的に決められるものなのでしょうか?
できないですね。「ぜひこの作品を修復させてください」とこちらから積極的にお願いすることはありません。考え方として、修復は「しなければしないほどいい」が大前提。たとえ作品にダメージがあっても、その状態で作品が長い期間「安定してきた」のであれば、手を入れることでかえってリスクが増す可能性もゼロではありません。修復の必要がある場合もできるだけミニマムに行うよう心がけます。ただ、美術館などの収蔵作品の調査をすることがあって、調査書類を作る段で作品になんらかの緊急度の高い損傷や、問題を見つけた場合には(たとえばカビが発生しているとか、今にも落下しそうな剥離があるとか)、事故防止の意味で修復を提案することはあります。
「タイムライン―時間に触れるためのいくつかの方法展」(以下、タイムライン展)の図録や著書を拝読し、作品に介入する責任の重大さや、作品はどこまでの範囲を作品と見なせるのかについて考えさせられました。抽象的な質問ですが、田口さんにとって「作品」の範囲は、どこまでと考えられていますか?
修復するときはシンプルにモノとして対象を見るようにしていて、「作品の範囲」について考えることはあまりありません。作品の範囲は、作品ごとに異なるのではないでしょうか。たとえば、タイムライン展でも扱った井田照一さんは「Surface is the Between(表面は間である)」という有名な一節を残していますが、彼の場合もまた、作品の範囲そのものや表裏の概念を超えていこうとする制作のあり方が特徴的です。
井田さんの作品の場合は、調査するほどに「裏面」の面白さが見えてきて、ただ「表面」だけを展示して作品だと言い切れるだろうか、と感じていました。彼はあえて劣化しやすい素材を選んだり、時間が経つと匂いが発生することを承知の上である種の技法を選んでいたりする。そのあたりの背景も理解して語りに取り入れることで、初めて作品が作品として立ち上がってくるんじゃないかと。そこで、タイムライン展で展示した《Tantra》は、次元を行き来する作品のあり方を見せようと、表と裏を等価に扱って展示するプランを立て、素材や技法にかんする情報もすべて開示しました。

どこまでが作品の範囲か…難しいですよね。修復的手法が「語り」すぎて作品を脚色することがあってはいけないし、基本的には事実だけを客観的な目で捉え、報告する立場でいなくてはと思っています。その一方で、保存修復的な視点から見ると作品の情報がより豊かになったり、わかることが増える面白さもたしかにある。それらを展示に取り入れるとどうなるだろうか、とずっと考えてきたんですが、タイムライン展で作家の皆さんと丁寧に展示を組み立てるなかで、それが少しは実践できたかな、という感じです。
とくに《Tantra》では「作品の表と裏の間を自分の身体が縫い歩くように行き来する」という体験を通して、作品に積み重なるもの(時間や素材など)の厚みを感じました。想像以上に作品は自由なのだ、という発見がありましたね。
「どの作品をアーカイブとして残していくか」も一つの判断であるわけですが、それはさきほどおっしゃった「己を消すこと」と矛盾するのではないでしょうか?
大事なご質問ですね。いつもそのことについて、いろいろと考えては苦しんでいます。己を消してアーカイブするとなると、全作品を収集することになってしまいます。でも、それは物理的に不可能ですよね。取捨選択すると、そこにおのずと己が出てくるものですし。私がこの仕事をしていく中で、先生のあの一言を思い返すうち、やっぱりそれは無理なんじゃないかと思うようになったんです。
「一番大切なことは、どれだけ自分を消すことができるかだ」という言葉ですね。
はい。でも自分を消すなんて、どうしたってできない。心構えはそうありたいとしても、仕事をしていればその人の手癖や目の癖がどうしても出てくるものだと思うんです。それらを一旦引き受けた上で、どのようにこの仕事をしていくかを考えたとき「何を考えて、何を選び、結果、自分は何をアーカイブすることを決めたのか」を残すことが、せめてもの責任の取り方じゃないかな、と。
それは具体的に言うと、どのような修復方法を選び、どのような手順で作品に介入したのか、またどんな素材を使用したかを明記して残しておくことです。さまざまなメディアを駆使して選択の根拠や背景を残しておくことで、将来的に作品に再び出会う誰かが、残された課題をどう乗り越え、作品にストレスの少ない方法でより長く残せるかを考え続けていけると思います。
最近では修復士とコラボレーションして、ブロックチェーン上に修復歴を残すプロジェクトもあるみたいですね。
たとえば仏像の胎内には空洞があって、そこに修復に携わった人々の名前や日付が書かれた銘札が入っていることがあります。本体自体の内側に記録を抱られる構造になっている。そんな感じで作品の修復記録が残されていると、修復士としても助かりますね。イタリアで仕事をしていた時に調査した作品の裏面に、小さな字で「少し表面が白くなっていたので、何月何日にオリーブオイルを塗っておきました」と書き込まれているのを見つけて、面白かったのを覚えています。100年以上前の小さな一文でした。曇ってきた絵に油を塗ればテカテカ光って綺麗になるだろうと思ったのでしょうね(笑)。
作品の生と死―完成以後の作品と他者はどう関わるべきか
ご著書を読んでいて、修復士の仕事はお医者さん―とくに外科医のようだと感じました。手術をする時に患者の状態をチェックしてカルテに記録し、次に体の内部に直接入っていくというステップも、医者の手つきそのものです。同書で引かれている、20世紀イタリアの美術史家・ブロカッチが修復を必要とする絵画を「病人」と例えたように*、この見方は一般的なようにも思います。修復のコンテクストにおいて、作品が人間の生命に例えられることが多いのはなぜでしょうか?
*「ここに、特定の「病気」は存在しない。「病人」がいるだけである」(田口かおり『保存修復の技法と思想: 古代芸術・ルネサンス絵画から現代アートまで』、平凡社、2015年、18頁)
いくつかの理由があるとは思いますが、近代修復が生まれ、今につながる修復の考え方が確立したのは意外と最近のことで、1900年代前半頃くらいなんです。その頃から職業としての修復家がでてくるんですが、それまでの修復の実態は、時として暴力的と言っていいほど乱暴なものも珍しくありませんでした。懐古趣味が流行ればコーヒーの粉やイカスミで表面に古色を施したり、「下の層に古い絵があるから、上の層はどんどん洗おう」と絵を過剰洗浄してしまったり……時間経過のなかで作品の姿が(ある意味では)できあがってくる、という意識が著しく欠けていた。
それはまずいのでは、と声高に言われはじめたのが1900年代前半。経年層の見直しや、「時間経過で成長する個体としての美術作品」という捉え方、またダメージや欠損も作品の一つのあり方だ、という考え方が出てきた。このような考え方は、人間の身体や健康に対するそれと通ずる部分もあるかもしれません。過去の修復への反省と、より長いスパンで作品の価値を考えていこうという思想が、今の作品の「生」への語り方につながっているのではないでしょうか。
海外のいくつかの国の美術館では、作品の「死の権利」が認められているそうですね。
はい。ある海外のコンサバターが「作品が展示できない状態になると、美術館は収蔵庫に設けた “仮の墓場” とでもいうべきスペースに仮死状態の作品を保管する」という話をしてくれました。「作品にも死ぬ権利がある」という文脈で個々の作品の保存可能性について語るのは、個人的にも面白いなと思います。
仮死状態になったとしても研究用には参照できますが、展示不可の時点で美術館の展示物としては修復できない―つまり、作品はある意味での「死」を宣言されるんだな、と。ただ、どういう状態が作品にとっての死なのか、いつ作品は死ぬのか……どの作品を触るときも考えますが、明確な線引きは非常に難しく、根拠を明確にすることにもさまざまな問題があると考えています。「これは死んでいるので、修復できません」と言ったことはまだありません。

先日「ウルス・フィッシャーのワックスでできた作品を100万ドルで購入した美術館が、アーティストの意図や作品の性質を重し、半年かけて毎日火を灯して少しずつ溶かしていく」という記事を読みました。蝋は完全に溶かされたあと、再度鋳造されるそうです。美術館というパブリックな場所においても、アーティストの意向がしっかりと反映されていることに純粋な驚きがありました。
一方、著書で語られている作品は、作家の手(テリトリー)から作品が離れた状態で大部分の議論が進んでいて、だからこそ「作品は誰のものなのか」をあらためて考える契機となったんですね。私はキュレーターという立場上、アーティストと仕事をしているため「アーティストの意向」に焦点をあてて考えがちです。ですが、作品をより長い目で後世をも射程に含む「公共財」として捉えると、一旦作家から切り離し「作品自体」とも対話する必要があると考えさせられました。
作品に不具合が出たとき、ふつうは作家に相談しようと思いますよね。作った人に相談するのが一番だと。ただそこで作家が修復を快諾した場合、修復するのではなく「改訂」される可能性もあって、保存修復史においてはそういった指摘がたびたび出現してきました。作家の手元から戻ってきたとき、もはやそれは修復を依頼した時の作品とは違うものになっている可能性があるなら、作家は修復行為から切り離すべきだ。そう主張する声も多く、一つの意見としては理解できます。
ただ、この分野で仕事をしていて思うのは、作家と会話することほど豊かなことはない、ということです。制作中に何が起きて、どんな素材を使い、どんな技法で、どんな状況で描いたかを知ることができる。「実は描いているときにこういうことがあって」「素材はこんな風に選んで」みたいな裏話が出てくることもありますし、その話から修復のヒントが見つかることも大いにあります。
なので、作家を修復の現場から排除することに私は反対です。科学的な解析結果をもとに、作家と修復の方向性やリスクを話し合いながら対処法を決められるのが一番いいと思います。みんなで作品の先を考えていけると理想ですね。
キュレーターという言葉は「cure(世話をする)」が語源にあるとよく言われます。しかし、実際に作品の「世話」をしているのは、キュレーターではなく修復士ではないかと思い至りました。あらためて考えてみると、キュレーターが世話をしているのは「文脈」であって、修復士が世話をしているのは物理的な作品なんですよね。作品を守る修復士あってこそのキュレーター、なのではないかと。
私の中では、キュレーターはオーケストラの指揮者。個性ある演者をまとめて、一つの作品を作る人、一期一会の出会いの場を作る人、というイメージです。修復家は、一人ひとりが使う楽器を磨いたり、調弦したり、革を貼り直したり、よりよいコンディションに持っていけるよう手をお貸しするという感じかなと。
ものすごく不安定な状態の作品があったとしても、諦めずにどうすれば展示できるかを探るのも仕事の一部だと思っていて、「これは修復できません」「展示できません」とはできるだけ言いたくないんです。まだできることがあるはずだ、といつも思う。現代美術は特にものによって素材や形、経年変化の仕方も違います。それぞれに最適な展示の方法が自ずと導かれる近代以前の絵画のように、一様に「何がベストか」がわからないことも多いのですが、そこが面白い。作品を展示できる状態に持っていくことで、初めてキュレーターに作品を採用していただけるわけで、まずはそこに作品が到達できるよう方法を探る仕事なのかなと思います。
いろいろな比喩が出ましたが、田口さんとしてはどんな姿勢で作品と向き合っていますか?
医者の気持ちになったことはないんですよね。そこまで大きなことはできていないと思っていて。近くで鑑賞できてラッキーな人、みたいな感じです(笑)。やっぱり、作品を至近距離で、表や裏から構造を見られるのはこの仕事の一番面白いところだと思います。この見る、というのが大事。目に入ってくる情報から素材や状況の仮説を立てていかなくてはいけないので、しっかり観察するよう気をつけています。ただし、現代美術は時間の蓄積が長くはないので、仮説を立てるのも難しく、応用が利かない場面も多いですが。
それこそ、作家に聞くことが一番の近道ですよね。
そうですね。あとは、その作品を展示したことのあるキュレーターの方や、展示の現場に入っていた技術者やハンドラーの方に聞くこともあります。いろいろな人の「目」を集めて整理して、情報を再構成していく中で作品を立ち上げていく。
「修復士」という言葉からは、コツコツと地道に手作業をしているようなイメージがあると思いますが、手を動かさないでぼうっとしている時間も長いんです。作品の前で、ただ「見て」いる。でも、それがほんとは大事な時間で、どこまで見えるかなぁといつも考えています。作者とお話することも大切なことですが、作者がご存命でない場合や、遺族の方や関係者の方も不在の場合には残されているものと話をするしかないので、その時はひたすら見ることで情報を拾うよう、とくに努めます。
お話を伺っていると、作品と修復士の関係性はドキュメンタリーにおける「事実」と「語り手」の関係性にも近いと感じました。介入した時点で主観からは逃れられない、という点も。
修復も、やはり「私自身がどう見たか」が入ってきてしまいますからね。だからモノを対象とした語りの場合は、語る人が多い方がいいと思います。どういう視点で作品を見たか、サテライト的に多くの語りがあることで作品の捉え方が立体的になる。そのサテライトの一つに修復士が見た作品の姿もあるといいですね。美術史家、キュレーター、インストーラー、鑑賞者など、さまざまな証言から一つの作品をひたすら語る……みたいなことができたら面白そうです。
ドキュメンタリーでも取材対象がご存命でない場合、よく知る関係者が語ることで本人の像を浮かび上がらせる、という手法がありますね。
たとえ作品が存在せずその記憶しかなくても、いろいろな人が作品を語ることで、作品は生き続けることができるはずです。素材の分析結果だけでも、ものとしての特性は記録され続けるわけですし。そういう「残り方」も、一つの保存修復の在り方、方法論としてあると思います。
今後はデータ上にしか存在しない作品が増えていくでしょうから、修復の在り方も変わっていくのではないでしょうか。
そうですね。データは量も膨大で、再生機器がずっとあるとは限らないので、常に乗り移れる母体を探し続ける、ゴーストのような状態になっていかざるを得ないケースもあるでしょう。エミュレーションを考え続ける必要がある点は、オールドメディウムによってある程度の持続性や堅牢性が担保される絵画や彫刻とは大きく違ってくるところだと思います。
たとえ再生できたとしても「昔よりも音や光が綺麗になってしまっていて、本来の粗さや雑味が消えてしまった」というケースもあり得るわけで。違うメディアで再生・再生産するとしても、当時の記録が映像や語りで一つでも残っていればブリッジがかかり、受け止め方にずいぶん違いが出るはずです。だからこそ、今後は収蔵の際に記録をきちんととることが重要になっていくのかなと思います。