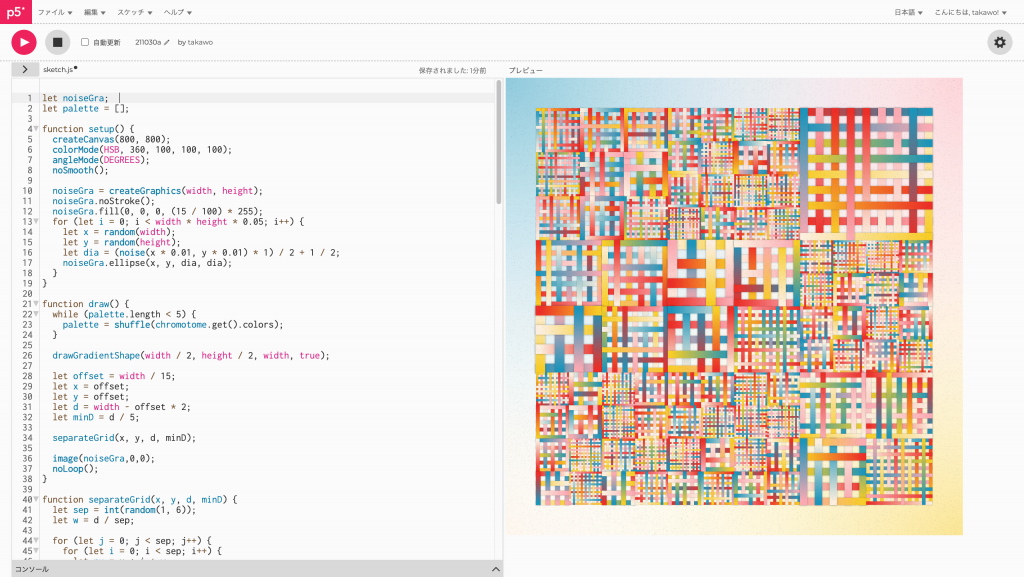ナイル・ケティングの最新作「Remain Calm」(2019~)は、世界4カ国、6つのプロジェクトにてフィーチャーされ、ロックダウンに揺れた非常事態下のパリ・パレドトーキョーで行われた「Anticorps」(2020)にも出展された。鑑賞者やパフォーマンス時の環境など、作品空間に付随する不確定要素をも即興的に受け⼊れながら展開する、サイトスペシフィックな性質をもつパフォーマティブ・インスタレーションである本作は、どのような着想で作られ、それぞれの場所で上演されたのか。現在ベルリンを拠点とするケティングに話を聞いた。
パフォーマーのクリエイティビティを増幅し、観客をも受け止める「閉じたエコロジー」
今回の作品概要を教えてください。
2年前、パリのレジデンスに滞在していた際にフィールドワークをしたものが原形です。パリのセーヌ川沿いにはたくさんの美術館があって、洪水で作品を避難することが多い。そのため、各美術館にマニュアルが整備されているのですが、私はそれをリサーチをしたいと考えました。いくつかの美術館のセキュリティーの方と話をして、作品の修復方法や、作品の保全、危機的状況になった時にどのように作品をケアするのかを中心に調べていきました。
そのプロセスの中で、小学校の避難訓練を思い出したんです。スピーカーから物が壊れる音が鳴ってテーブルの下に隠れ、アナウンスが流れると外に出る。この「皆が同じ空間と状況に居合わせているけど、それはシミュレーションである」という状態が、公的劇場でプレイされるような筋書きのある演劇に思えて。
パフォーマンスや劇は、常に観客がいることを前提にしていますが、私が興味があるのは、演じている人そのものが変化していったり、演じている人の感情に訴えかけるものが、たまたたま居合わせた観客に共有されていくことです。避難訓練は自分が今までリサーチをしていたものにすごく共鳴したので、だんだんと作品を「美術品を避難するためのシミュレーション」とすることを考えました。
パフォーマーはある作業を繰り返しているだけですが、美術館の中でこれを「作品」としてプレゼンテーションをすると、結果的にパフォーマーの身体も作品になる。「自分自身が作品になると同時に、作品の保全もしないといけない」というパラドックスを作品の中で生み、それをずっとランしていくことで「閉じたエコロジー」を作っていくんです。

環境に制約がなかった上海でのパフォーマンスと、今のように日常自体が災害化した中でパフォーマンスにはどのような違いがありましたか?
その点については私もどうなるのかと思っていました。タイトルやコンセプトが今の状況に呼応している部分もありますから、観る人によって解釈の幅が増えていますよね。中でもパリの展覧会ではパフォーマーはマスクをしたり、消毒ジェルを持つ必要が出てきましたが、この制約の中で作品を立ち上げても作品には支障がなく、むしろリアリティーが強くなったのは驚きました。
私が作品を作る上でいつも大事にしているのは、作品が的を射た方向へと進んでいくのではなく、どんどんと広がり、宇宙のように来るもの全てを飲み込んでしまうような、作品自身ですら制御ができない「伸びしろ」を持たせてあげることです。作品は観客やパフォーマーを包み込むよう設計しているので、そこでまた異なったナラティブや意味を観客が見出すことによって作品が複雑化したと思います。危機的な状況や制限のある状況の中だからこそ、私が大事にしている「作品を閉じず、常に開き続けること」が機能したんじゃないでしょうか。

先程の「閉じたエコロジー」という言葉が印象に残っています。作品は開かれつつも、その中にエコロジーがあったからこそ、コアの部分を保持できていたのではないかと思いました。
私の活動ではコラボレーターを輝かせるのではなく、自身も含めてアーティストとしてプロジェクト中に吸収されるように、閉じた空間に一緒にいることで、多様なクリエイティビティーが出てくると思っています。アーティストの概念が重要でなくなっていく部分に、演者を配置する構造をつくっていくのが大事で、構造さえできてしまえば、色んなものを受け止めてくれる「閉じた空間」になる。作品を作っていく上での一番のセーフティーネットのようなものですね。そこに吹く風、そこを動くオーディエンスによって常に作品ができ上がっていく。展覧会に毎日表出する作品を「閉じてあげること」はよく考えます。
あなたの作品の中の「連帯」が嘘っぽく見えないのはそれが理由かもしれませんね。
連帯やつながりといった構造のためには、自分をコントロールの利く場所に持っていく必要がありますね。自分をよく分かっていないと、人と繋がることはできないじゃないですか。IPアドレスがないとどこへもアクセスできないのと一緒で。
私たちが生きているこの社会は「個人性」や「個」を感じる機会を全く与えてくれない。だから社会の中でどのように人と繋がっているかを考えると、個々がありながらも個がない「ペースト状の繋がり」のほうがしっくりくるし、理想的な関係性を作る上でも近い感覚だと思っていて。個のテクスチャーではなく、ペースト化された集合体に興味を持っています。
それがあなたの言う「サステナビリティー」ですよね。一般的なサステナビリティーよりも「共存」を意図していて、その共存は虚構の上に成り立っているというより、皆が一つの器の中に入るというような意味合いが強い。
その意味では「Sustainable Hours」(「曖昧な関係」展@銀座メゾンエルメス/2016)は私のサステナビリティーや時間の考え方、オーディエンスとの関わり方を初めて形にしたもので、多くのグレーゾーンを生み出すことができた作品でした。

自分がアーティストとして展示をする中で、長い歴史で形作られた美術館やギャラリーのシステムを無意識的に用いてしまうことに恐怖を感じたことがあります。新しさや斬新な手法でもって作品を提示をすることにも、将来性を見出すことができなかったんです。永遠に終わらないゲームのように思えてしまった。だったらむしろ、相手に寄りそうことで、お互いに気付かなかったグレーゾーンを生み出していけないか。そうすることで美術館、アートという空間がもっとサイト・スペシフィックな意味合いを持ってくるのではないかと。そのマテリアリティーをもう一回感じ、楽しむことができないかと思っていました。
作品は常に解決され続けることで作品になる
CashmereRadioに出演された際「作品ならミスもエラーも作品になる」という話をされていましたね。この発言の意図と、なぜ筋書きやタイムラインのある作品を作ったのかを伺いたいです。
最近は資本主義が加速した結果、なぜか本来のパフォーマンスそのものと、ショービジネスとして人に見せるためのパフォーマンスの区別があいまいになってきています。でも、もともとダンスやパフォーマンスは神や超人間的なものと繋がるためのデバイスであり、方法論でした。私が興味があったのはそういった総体的なパフォーマンスであって、舞踊や地方で行われる秘儀などにある動きやメソッドは、強い力で、人間が整理整頓できないものの中で出てくる作法(プロトコル)だったりするんです。パフォーマンスやダンスが観客を想定しただけのイベントになってしまうのはすごく悲しいですね。


例えば私がパフォーマーとして他の人の作品の中に関わると、制作のプロセスの中でたくさん感じることがあります。人に見せることだけではない。たくさんのエラーや間違いがある「人に見せていない部分」まで含めて、一つの「パフォーマンス」だと思うんです。本番だけではなく、ウォームアップや水分補給まで含めた動きや空間の変化を見てみたいし、それに自分も飲み込まれてみたい。失敗を排除してしまうと、ただ人に見せるためのものになってしまう。そういうものでないものを感じてみたいです。
作品が失敗することと、作品の中で失敗が起こることとは、大きく違います。特に「Remain Calm」では、使用するテクノロジーにきちんとフレームをしてもらって、マットレスのように受け止めてくれる構造体にしていて。映像や光源にエラーが起きてもキャッチしてくれるような空間をつくるために、テクノロジーを多用している部分はありますね。

「災害」という主題から殺伐としたパフォーマンスを想像していたのですが、すごく居心地のいい空間で、何時間でも見ていられるような作品でした。お客さんを受け入れるためのエコシステムが機能していて、かつ人間味や血が通っているのが大きかったのかな、と。
そうですね。生身の人間と仕事をしているんだったら、やっぱりその人のことを知りたいし、その人が一番面白く見えるようなテクスチャーを見てみたいです。そこで「失敗をしていけない」という規定をつくってしまうと、それが一つの筋書きになってしまう気がしていて。そのため、私のパフォーマンスではパフォーマーにインストラクションを渡しますが、そのインストラクションを無視することもOKで、特に今はコロナウィルスのこともあるので、展示室に人が多く、危険を感じたら部屋を出ていいと伝えてあります。作品はその時々の要素によって瞬間瞬間で成り立っていて、常に「解決」をされていく中で作品ができていくんです。
解決されていく中で作品になる?
はい。例えば、パフォーマーがどうするか迷ったり困惑しても、何かしらの方法で解決をしていくわけですよね。私が書いたインストラクションを使ったり、部屋を出ることで解決したり、水を飲むことで解決したりする。そうやってトラブルシュートしていく空間そのものを作品としている。私の中でのいいパフォーマーとは決して「いい動き」をする人ではなくて、トラブルに対していい形でトラブルシュートできる人たち。そんな人と仕事をしたいし、関わりたいなと思います。
作品を観賞している自分自身も作品の中にいるのか、それとも傍観者なのか。その間で揺れ動いてしまいました。
その意味でしっくりきているのが、セノグラフィー(舞台芸術)という考え方です。ブルーノ・ラトゥールの著作『地球に降り立つ:新気候体制を生き抜くための政治』(新評論・刊/川村久美子・訳)の中ですごくいい部分があって、彼は今の世界を舞台に例えて
ところが今日、装飾部分、舞台の袖、背景、ビル全体が舞台の中央に躍り出てきて人間と主役の座を競う。脚本のすべて、エンディングさえ書き換える。いまや人間が唯一のアクターではないのである。もっとも、現実とかけ離れているとはいえ、人間自身は依然、重要な役割を担っていると思っている。
と書いています。
セノグラフィーが、見ている人やパフォーマーをどんどんと飲み込み、最終的に作品がどこにあるのか分からないような状況にまでなってもいいのではないかと思います。そういう意味では「セノグラフィー」は私の表現したいことを的確に表してくれている言葉ですね。

絶えず新たなネットワークにアクセスするセンシティビティ
作品鑑賞で得られる体験として、知識やテクニックに感動したり、想像力をかき立ててくれることが多い一方、ナイルの作品には癒し効果があると思っています。「Sustainable Hours」や「Whistler」展(@山本現代/2016)もそうでした。夕暮れとともに色が変わっていくのを見ることが非常に心地良かったんですよね。
私がすごく嬉しいなと思う要素の一つに、プロジェクトに関わる人にも得られるものがあることです。キュレーターや、他のアーティストが私の部屋に来て「はぁ〜」と一息ついているのを見ると、こういった瞬間にも意味のあることができたのではないか、と思います。以前展示をしたドイツ・ハノーファーの展覧会では、毎朝キュレーターが私の作品のためにコーヒーを淹れる作品で……だから、キュレーターをバリスタに変えたわけですが(笑)。
毎日やっていると、それが一つのリチュアル(儀式)になってくるんですね。コーヒーを淹れて、インスタレーションの中に置いて、オフィスに戻って仕事を始める。そのレベルの感覚に寄り添うものにすごく興味があります。私がインストラクションを組むときも、パフォーマーが疲れないよう休憩時間やそのタイミングを意識します。ツアーコーディネーターみたいですね。
ナイルの作品は、インターネットの一番アクセスしやすいところにある、キャッチーなタイトルをつけられるコンテンツから遠い存在ですよね。ナイルの作品で得られる経験は、インターネット上で見つけることが難しい。でも誰しも、毎日、キャッチーなタイトルを付けて配信できるようなマイベストを出し切って頑張りたいわけではない。だから生産性からは遠い、ただゴロゴロしているネコ動画がこんなにも流行り、人々の癒しや活力になっているのかもしれないな、とふと考えていました。
何も起きていないことから得るものは、「与えられているもの」とは全く違う部分の感覚に訴えかけるものがあります。ある意味癒しや活力によって過激であり、パンクであり続けたいです。パンクであることは別に何か法則を破ることだけではないと思っていて、特に今の社会だと規則に1000パーセント従うことによってパンクになれることもあるはず。現代の反骨とはどういうことなのか、といつも考えています。
その「パンク」や「ラディカル」についてもう少し掘り下げさせてください。
世の中に偽りが多いから、正直であることがだんだんとラディカルになってきているように感じます。子どものような存在や、動物、バクテリアなどの人間ではないものがラディカルに映るのも、人間が制約の中で上手くやりくりをしているからではないかと。
少しずれるかもしれませんが、ナイルの作品の中に生け花があることもラディカルとの親和性が高い気がします。最近は生け花も余計にラディカルに見えますよね。
私が興味を持っているのはプロトコル(儀礼)としての生け花。最終的に生け花がどのような形になるかは関係なくて、それがあることで起こるプロトコルに興味があります。お茶も、最終的に味わう「お茶の味」よりは、お茶を飲むところにたどり着くまでのプロトコルがあって、アウトプットはプロトコルを通るための一つの中継地点のようなもの。生け花や茶道、華道の中で、どのようなプロトコルによって人を動かしているのかに興味があります。

例えば、会社に行ってオフィスで仕事をして、メールの最初に「Dear」と付けることも全てプロトコルだし、メールの打ち方や文末の作り方も、全てコレオグラフィーです。私たちはそこで新しいアウトプットを求めているのではなく、そのプロトコルを踏んでいくことで中継地点をやり過ごしている。その意味では、パフォーマンスもプロトコルだと思いますよ。中継地点にたまたまオーディエンスがいて、たまたま作品になっている。そんなことを感じるのに、生け花は良いサンプルなんです。
我々が常に新しいことを求めていたせいで、新しいこと自体がラディカルではなくなった気がします。
良くないのは社会が一つの方向に向いてしまうこと。アーティストも常にそう意識して、作品が―作品ではなく制作の仕方も含めて―何か違うことに気付かされるものを作ることができれば、私はそれだけで作品を制作する意味があると思います。
「新しいし、ネットでもすごく反響があるから面白い」のではなく、その人の喋り方、ファッションや仕事の仕方、ライフスタイルにはっとさせられることも含めて、作品を作っていきたいですね。
時代の要請の速度が速くて強いから、オリジナリティーについてはかなり意識的に踏ん張っていないと流されてしまいますよね。
本来は何もしないでも、ちょっとした一つの動作で自分のオリジナリティーが見せられるはずですよね。でも今のSNSではそこまでキャッチすることができない。見る側も作る側もセンシティブであることが必要になってきている気がします。
最近は、繊細であることがどのようなことなのかをよく考えています。私の考えるセンシティブであるということは、肌や自身の敏感さではなく、他のネットワークを感知する感度の高さと、絶えず新たなネットワークにアクセスしていく能力です。アーティストも、観客も、オーガナイズをする側も、センシティビティーの力をさらに高め、個々の思考のリプレゼンテーションではなく、個人では感じることのできない感覚や思考を、アートやアート以外を通じてエクスペリメンテーションすることができれば、さらに面白いネットワークにアクセスすることができるのではないかと思います。