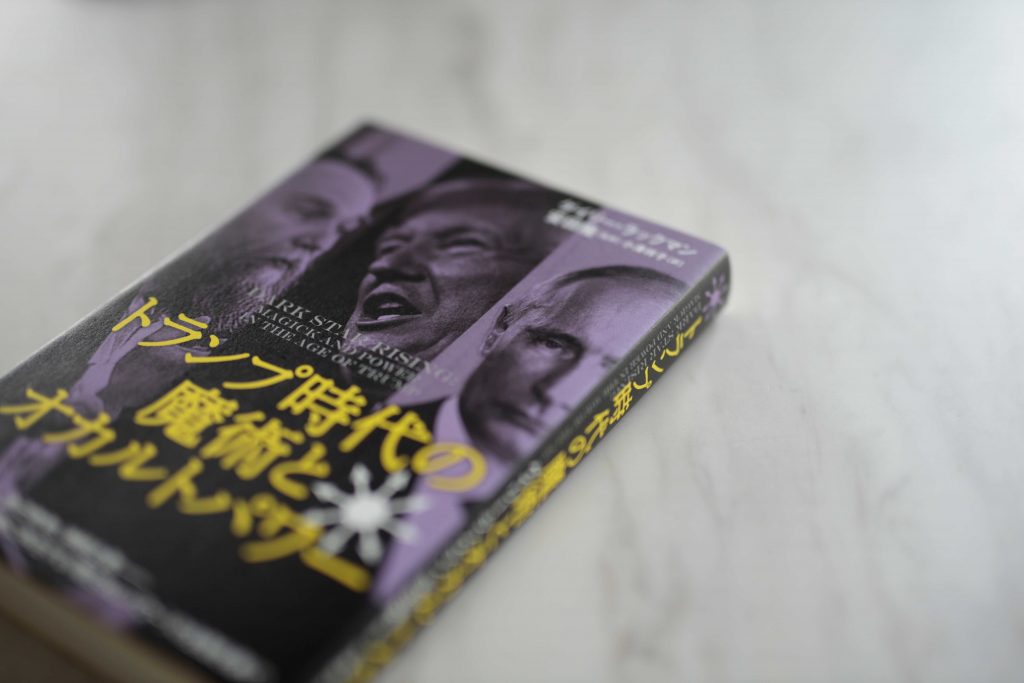怠惰は難しい。ほとんどの人間は怠惰に耐えることができない。できて数時間、それ以上となると、いかにしてこの怠惰から逃れるかだけを考え始め、そして突然思い出したかのように直立すると、いそいそとコーヒー(もしくはモンエナ)を片手にモニターの前に戻り、中断していた仕事をおもむろに再開するのだ。
なぜ人は怠惰に耐えることができないのか。なぜ人は怠惰を真正面から享受することができないのか。なぜ人は怠惰に対して真剣に取り組むことができないのか。言い換えれば、なぜ人は怠惰に対して中途半端に、やる気なく、つまり怠惰(!)に取り組むことしかできないのか――。
時間を無駄に食いつぶしているという感覚から来る焦燥感、周りが働いているのに自分だけが怠けているのではないかという罪悪感、等々……。「生産性」に対する強迫観念が、我々を活動へと不断に駆り立てる。後期資本主義においては、高速で流れ去る時間のスピードに取り残されることは、それだけで重罪であるかのように響く。私たちは、ベンヤミンが愛したクレーの「新しい天使」に描かれた天使のように、できればそこに留まりたいのに、「進歩」という名の嵐によって未来の方へと押し流されていく。クレーもベンヤミンも、堆積した瓦礫の上に怠惰に寝転ぶ天使の姿など想像することさえ叶わなかったであろう。これこそ近代の悲劇でなくてなんだろうか。
そう、怠惰の実践には修練が伴う。怠惰を学び、実験と失敗を繰り返し、そして長年のストイックな修行の末に怠惰の奥義を獲得した者だけが怠惰を十全に実行し、それを完成にまで高めることができる。怠惰に対して怠惰な者は、怠惰の真髄を知ることは遂にないだろう。この深奥なる逆説に知悉した者だけが、怠惰という名の美酒を味わうことができるのである。
近年、ストイックな怠惰の実践者がそこかしこに現れ始めている。三千年の歴史を誇る中国では、「寝そべり族」なる若者たちが、ディオゲネス的な哲学を用いて現代中国に犬儒学派のエートスを復活させんとしている。消費も結婚も拒絶し、労働は最小限に留める彼らの「寝そべり」主義は、親世代が押し付けるエリートコースからの意識的なドロップアウトであり、ひいては後期資本主義が押し付ける競争の倫理に対する断固とした「否」の表明でもある。「がんばったって、どうせ報われない。社会の階層はすでに固定化されていて、ちょっとやそっとでは変わらないのだから。一生働いても家を買えないのなら、最初から買わないほうがいい」(中国で、若者の「世捨て人」化=「タンピン主義」が大議論を巻き起こしていた…!(中島 恵) @gendai_biz)
同様に、欧米では20〜30代の間で「FIRE(ファイア)」と呼ばれる早期リタイアがムーブメントとなり、方や我が国でもサンデル教授の能力主義批判本がにわかに耳目を集めている。こうした時流には、上世代が押し付けてくる「豊かな人生設計」や消費文化に対する疑念、苛烈な競争主義に対する幻滅感などが大きく影響しているのだろう。
もっとも、ここ日本においても、そうした現代社会からの意識的なドロップアウトの表明や実験は、現在に至るまで散発的に見られてきた。たとえば、安い土地に10万円で小屋を建ててDIYな暮らしを営むBライファーたち。またはネットの仄暗い片隅で蠢く、サイレントテロなるムーヴメント。曰く、さまざまな社会活動――消費行動や人間関係、ひいては自らの生存そのものを消極化、縮小、または消滅させていくこと(サイレントテロとは 一般の人気・最新記事を集めました – はてな)。サイレントテロの教義にあっては、何もしないことが、そのまま社会に対するテロになりうる。あるいは、元「日本一有名なニート」で現作家のphaによる一連の著作、等々……。
ここに紹介する梅崎春生『怠惰の美徳』(荻原魚雷編)もまた、そうした連綿と連なる怠惰の系譜上に位置する、というよりかは、そうした系譜の原点として遡行的に見出された、とも言えよう。そう、同書の編者である荻原魚雷によって。彼もまた、怠惰の探求者の一人に他ならない(このことはいくら強調してもしすぎることはないだろう)。
さて、唐突だが梅崎は同書のなかで、「姿勢」に対するこだわりを表明している。
私は怠けものです。怠けものというよりは、どんな場合でも楽な姿勢をとりたい性質です。近頃そうなったのではなくて、生まれつきそうなのです。しかし楽な姿勢といっても、日向に寝そべっている猫のような、あんな無為は好きでありません。少年の頃見たことがあるのですが、風の吹く枝に逆さにぶら下がっている蝙蝠のような形。あんな形が好きです。また早瀬のなかで、流れにさからって静止している魚の形。あの蝙蝠や魚は、風や水を適当な刺戟として感じながら、自らの姿勢を保ち、且つ楽しんでいるに違いありません。いや、楽しんでいるかどうかは知らないが、あれが彼らにとって一番楽な形であることは、確かなことでしょう(18頁)
不動の姿勢をゆるやかに保ち続ける魚や蝙蝠は、しかし単にそこに無為のまま横たわっているのではない。彼らは川の素早い流れや風の勢いに対して逆らいながら自分の姿勢を保ちつつ、なおかつ外部からの刺戟を楽しんですらいるかのようだ。梅崎はまた次のようにも書いている。「自分を適当に揺れ動かすこと。この適当な振幅の測定がむつかしい」(19頁)。流れに逆らう魚は、小刻みに自らの体幹を揺れ動かし続けることで(意識的にせよ無意識的にせよ)その姿勢を保つ。その微妙なバランス感覚。この適当な振幅の測定を一瞬でもはかりそこねると、姿勢が崩れ、そのまま押し流されていってしまうことだろう。クレーの天使を押し流した、あの「進歩」という流れによって。ことほど左様に、怠惰とはまず何よりも姿勢のバランスにこそ関わるあり方と言えるのだ。
梅崎春生は1915年生まれ。終戦直後の1946年に「桜島」を発表し、野間宏、椎名麟三、武田泰淳らとともに「第一次戦後派」として活躍する。梅崎は、太平洋戦争開始直後に陸軍から招集を受けている。だが対馬重砲隊の営門をくぐるも、軽い気管支カタルを肺疾患と誤診されて、即日帰郷となっている(ちなみに、このとき入営した新兵のなかに『神聖喜劇』の大西巨人がいた)。その後は、東京にて東京市教育局の雇員として働くも、役所のブルシットジョブに嫌気がさし、同僚とともに「フィルム」と名付けた数奇な賭博のゲームを考案し、それに明け暮れた。このどこか滑稽で笑いを誘うサボタージュのエピソードも同書のなかで出てくる。だが、とりわけ筆者にとって印象的だったのは、戦時中の飯塚酒場についてのエピソードだ。梅崎と同僚たちは、夕方に役所の仕事が終わると飯塚酒場の行列に並びはじめ、入場して粗悪などぶろく酒を一息で飲み干すと、また外に出て行列の末尾につく、というサイクルを繰り返していた。戦況が悪化していくにつれ、行列は日増しに伸びていき、後尾は角を曲がり、更に伸びてまた角を曲がっていく。日が暮れる頃には、行列全体に酒の陶酔が満ちていくのがわかるようだったという。このあたりの箇所の記述はとても美しく、梅崎のユーモラスでヒューマンな作家性が遺憾なく発揮されているように思う。せっかくなので、引用してこの短い書評を締めたいと思う。
やがて一回目が終わって、二回目の先頭がふたたび店に入るころから、行列はなんとなく華やいでくる。この長い大蛇のような人の列に、ひとわたり酒が行きわたって、昼の間の緊張をときほぐすような黄昏のいろとあいまって、あの何ともいえない親しい温和な雰囲気にあふれてくる。この瞬間を、僕は何ものにもかえがたく愛した。黄昏とは、何といいものだろう。その黄昏の風物を――三河屋で見た夕月や、飯塚の柳や、堀留橋の蝙蝠や、カミヤバーの夕霧を、僕はいまでもなつかしく思い出す。今大急ぎであおった酒が、また列に加わっているうちに、ほのぼのと発してきて、風景は柔らかくうるんでくるのだ。この時僕は始めて、自分を、人間を、深く愛していることに気がつく。それはひとつの衝動のようにやってくる。(244〜245頁)