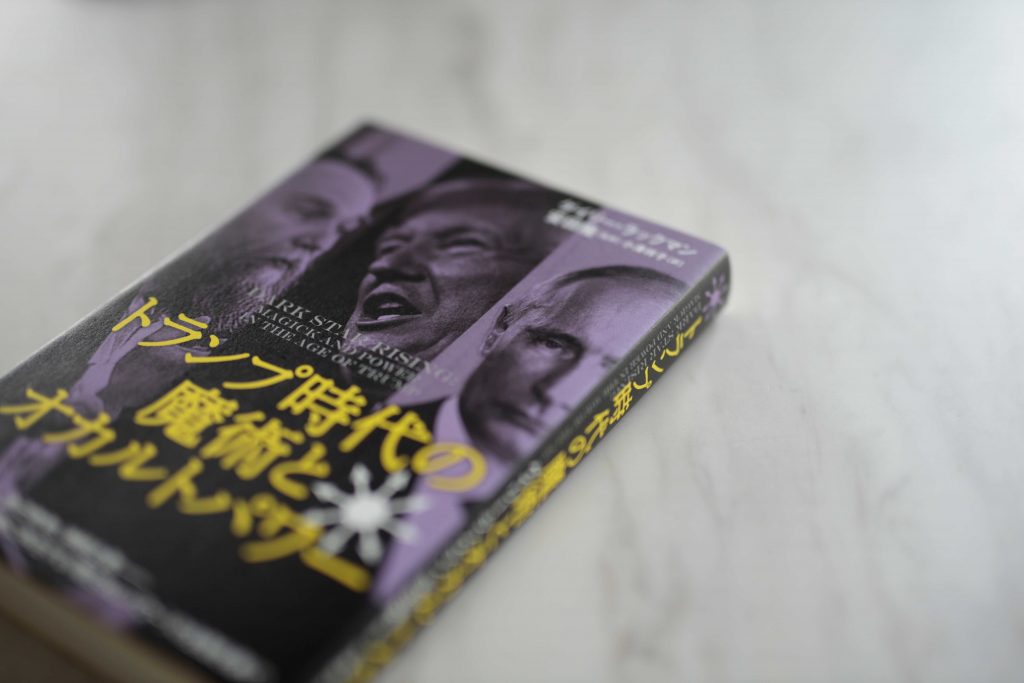残念なことに、筆者は詩を解する能力が皆無である。ただし、詩人の書く散文はとても好きだ。だから、筆者は岩倉文也の書く散文も同様にとても好きなのである。
二二歳の詩人、岩倉文也が散文によって書いた小説集『終わりつづけるぼくらのための』には、断片化された小さな「世界の終わり」の物語が約八〇篇収録されている。そのたびごとにただ一つ、世界の終焉。
この小説集のコンセプトについて、詩人は自身のツイッターで率直なまでに語っていた。以下のツイートは二〇二一年一月九日のもの。
美少女ゲームにおける残酷だが美しいBADENDをいかにして小説化するか……という着想から書きはじめた本作には、ぼくの考え得る全ての「終わり」を詰め込みました。詩ではあまり使わない「永遠」という言葉もたくさん使ってます。なぜなら「永遠」を求める心ほど切実で、救いのないものは存在しないから
美少女ゲームにおける残酷だが美しいBADEND。筆者も思い当たる。たとえば、二〇〇八年に発売された『リトルバスターズ! エクスタシー』。筆者は、その中のヒロインのひとり、小毬のBADENDがいまでも印象に残っている。学校の屋上、主人公と少女は互いに寄り添い、どこか遠くを眺めている。そこに至るまでの経緯や、細かい言葉のやりとりはほとんど忘れてしまった。けれど、このルートにおける最後の文章――最後の一行――だけは鮮烈に覚えている。それはこんな風だった。「二人は最後まで一緒だった。」そして画面は暗転し、BADENDであることが示されたのち、タイトル画面に戻される。
この文章における「最後」とは、ここでは「この世界の最後」をおそらく意味している。二人は最後まで一緒だった。一読して、この文章には大胆な省略が施されていることに気づく。「最後まで」とあるが、その「最後」は一体いつ二人に訪れたのだろうか。数十分後か、数時間後か、あるいは数日後、数週間後、はたまた数年後か、それとも……。しかし、そんなことは二人にとってはもはや関係がない。というのも、二人の物語はすでに終わってしまったから。いかなる変化も出来事も起きなければ、それはもはや記述しようがない。言葉はすでに役目を終え、空白に向かって雪崩れていく。その意味で、ここでの省略法は必然ですらある。そっけないほどの省略とともに、最後=世界の終わりが示されてしまっていることの、美しくも残酷なまでにあっけない感じ。二人は、物語の終わった世界で、終わりの到来を待ちつづける。最後まで。
閑話休題。ところで、『終わりつづけるぼくらのための』には多くの余白が含まれている。八〇の物語の諸断片、その隙間に不可避的に生み出される余白たち。
詩人はかつて、同人誌『インターネット2 VOL.2』に収録された「『lain』全話レビュー」という散文のなかで、次のように記していた。
荒涼とした世界だ、そう思う。この世界がいかに豊穣であっても、その印象を拭うことはできない。ぼくらは日々どれだけの物語を消費しているのだろうか。断片か否かに関わらず、つねに何かしらの物語に浸っている。漫画でもアニメでもエロゲでも小説でも、あるいはソシャゲでもツイッターのタイムラインでも構わない。ぼくらはきっと余白を恐れている。寝ている間でさえ、人は夢という物語をみてしまう。そして詩とは物語からの切断であったはずだ。余白こそが真に豊穣であると、書かれなかった物語にこそ価値があると示すための言葉。けれどぼくは――。
詩によって物語から切断されることで、あの余白の領域を、遂に書かれなかった物語を指し示すこと。だが逆説的なことに、余白とは物語が、言葉があってはじめて存在できる。何もない空間に「余白」は生まれ得ない。物語をバラバラに断片化し散逸させること、それは詩人にとって、余白を生み出し、余白に到達するための実践的な「方法」に他ならない。しかもその一方で、詩人は物語の切断を、詩ではなく物語それ自体によって達成しようと試みる。
如何にして。散乱した物語の断片群には、少女が頻出して現れる。それは詩人にとって、単なる記号的な存在に過ぎないのだろうか。そんなはずはない。詩人は、やはり『インターネット2 VOL.2』に収録された「少女写真のおもかげ」の中で、こんなことを書いていた。
ぼくが少女という存在に関心を寄せるとすれば、それは少女がなにを仕出かすか分からない存在である場合に限定される。平気な顔で虫を殺したり、誰かに切ない初恋を抱く裏で陰湿ないじめを行っていたり、ふいに神妙な顔で遠くをながめていたり……。大人の欲望の外へ外へと逸れてゆくもの。情緒的な秩序のほころびに位置し、決して大人が所有することのできないという点に少女性の本質があると僕は思う。
言ってしまえば、少女とは物語=ナラティブの秩序を壊乱させ、そこから常に逸脱していく存在なのだ。少女は物語を成立させる既存のコード=意味の体系に回収されることがない。すなわち、少女は物語をさながら詩のような、散文にとって異形のテクストに変換させてしまうのだ。変換器としての少女。そして、もはや一貫した物語を維持できず、バラバラになった諸断片の間に、あの余白が、すべての言葉も意味もその余白に向けて飲まれて行ってしまうような、そんな空無としての余白がそこかしこに出現しはじめる。
ここに至って、余白と同じ色を持つ白のイメージの氾濫がことさら重要に思えてくる。一読してわかるように、『終わりつづけるぼくらのための』には様々な「白」が現れては消えていく。雪、白い帽子、街を白く染め上げる乳白色の雨、白さを増していく桜、白くて半透明な皮膚、白く染まる吐息、白色の灰、白いカーテン、何かの数字を表示する白い機械、天使の死体、白い服を着た少女、そして雪、雪、雪……。
『終わりつづけるぼくらのための』における白のイメージは、端的にいえば詩人の「記憶」と直接的あるいは間接的に関わっている。本作を注意深く読むと、詩人はほぼ一貫して記憶について書いていることに気づく。幼少時代の記憶、家族の記憶、臨海学校の記憶、花火の記憶、そして、かつて過ごした福島の記憶……等々。その諸々の記憶を束ねる結節点とでも呼ぶべきものが、「ドア」で描かれる原初の記憶、それ以上遡ることができない、「ぼくのなかにあるいちばん古い記憶」。それは、雪の記憶。「玄関を出ると、白。白いものが、膝丈くらいまで積もっている」「取り残されたような、切り離されたような、燦々と白い、雪の記憶。」(一八三頁)
詩人は前出の「『lain』全話レビュー」の中でも、この原初の雪の記憶について書いている。この箇所は、詩人の詩作に対する態度が率直に表明されているという意味でとても重要に思えるので、やや長くなるが引用してみよう。
ぼくは庭に立っている。まわりにはいちめんの白。膝丈までの白。近くには母親が立っている。その気配をぼくは感じている。つめたい、とは思わなかった。どんな言葉も、出てはこなかった。ああ、白い。その激しい白さだけが焼き付いている。
これはぼくの記憶。これ以上遡ることのできない、いちばん最初の記憶。その日までぼくは、ゆき、という言葉を知らなかったのではないか。そんな気がする。
記憶。ぼくをぼく足らしめるもの。たぶん詩人にとっては、なによりも大切な創作の糧。
記憶。それは古ければ古いほど、純粋なイメージに近づいてゆく。映像。というのとは違う。ことばによる記録、というのとも違う。えいえん。もしくはそれに近いのかもしれない。純粋である。ということは、意味を持たない、ということ。
誰しもがもっていて、この世界でもっとも詩に近い場所。それが最初の記憶。いちばんふるい思い出。詩を書く本質的な動機、というものがもしあれば、それは、最初へ帰りたい、という願望以外にはありえない。まだ言葉もなかった場所。すべてが無意味で、すべてが純粋で、すべてが永遠だった場所。そこに少しでも接近するために、詩人は言葉を尽くすのだ。
白。それは、あまねく物語も言葉も意味も論理も蒸発してしまう、純粋な白熱。時間は停止し、すべてが凍りつく。そんな沈黙と永遠と無に満ちた領域に、詩人は言葉によって近づいていく。逆説的に見えるが、言葉によってしか、そこには至れないことを、詩人は知っている。白熱に近づいていくにつれ、言葉は透明になっていく。その向こう側にある、永遠の相さえ透かし見えるほどに。
物語=記憶=言葉の零度。語り得ない領域。そこに至れば、もはや何も起こらず、何も到来することはない。ここでも逆説的な事態。終わりの世界にあっては、もはや何事も起こることはなく、よって終わりの世界の終わりも遂に到来しえない。ぼくらは終わりの終わりを待ちつづける。
ぼくらは終わりを終わらせることができない。終わりに終わりはなく、よって、ぼくらは終わりつづけなければならない。また終わるために。
終わりなき終わりの反復の彼岸において、詩人はどこか誰もしらない永遠を見つめている。