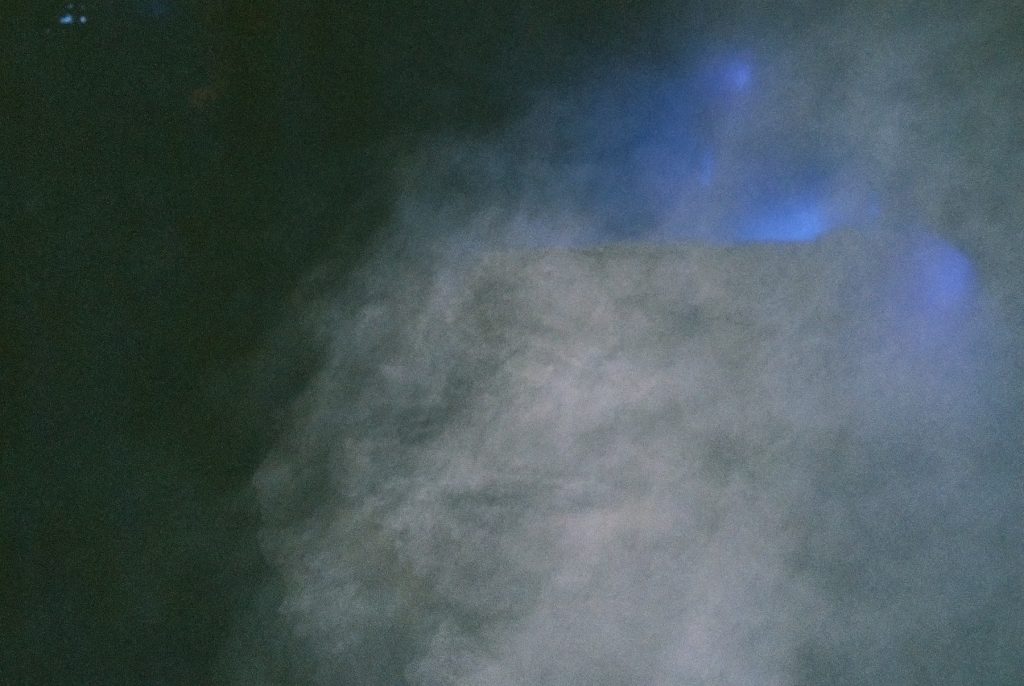小森くんという友達がいた。小学生のときのことだ。僕と小森くんは似ていた。子供は似たもの同士で友達になる。だから僕らは友達になった。小森くんは体が小さかった。僕も体が小さかった。小森くんは静かな子供だった。僕も静かな子供だった。僕らは漫画が好きだった。ゲームが好きだった。僕らはそういうグループだった。どこの小学校にもグループというものがある。どんな小学生にもグループはできる。グループは概ね、体の大きさや筋肉量や運動神経の多寡によって決められる。スポーツが得意な子供はスポーツが得意な子供同士でつるむ。スポーツが苦手な子供はスポーツが苦手な子供同士でつるむ。前者は不思議と妙に明るく、後者は不思議と妙に暗い。そして僕と小森くんのグループは明確に後者だった。誰がどう見てもそうだった。僕らは学校が終わると、小森くんの家で漫画を読んだりゲームをしたりして過ごした。小森くんは一人っ子で、母親がいなかった。でも小森くんはさびしそうではなかった。小森くんは幸せだった。幸せだったと思う。少なくとも当時の僕はそう思っていた。僕は小森くんがうらやましかった。小森くんの家では『コロコロコミック』も『コミックボンボン』も毎号買い揃えられていたし、『ドラゴンクエスト』も『ファイナルファンタジー』も全シリーズ揃えられていた。全部おばあちゃんが買ってくれたものなのだと小森くんは言っていた。僕が小森くんの家に行くと、小森くんのおばあちゃんは僕らにどら焼きや饅頭を買ってくれた。ときどきお父さんが家にいて、そんなときはドライブに連れていってくれた。小森くんのお父さんは僕らをいろんなところに連れていってくれたが、そのほとんどをもう覚えてはいない。楽しかった思い出がたくさんあるが、いまではその雰囲気だけが残っており、はっきりと覚えているのは、カードゲームのショップで、遊戯王のカードを買ってくれたことだけだ。あまりに現金すぎて、ひどい話だと思うが、子供の頃に与えられる強い印象というのは、そんなものなのかもしれない。
『実況パワフルプロ野球』というゲームがある。それは実在する日本のプロ野球チームやプロ野球選手を操作して遊ぶ野球ゲームで、とてもおもしろい。僕はそのゲームが好きだった。いまでもたぶん好きだと思う。いまではもうやることはないが、ときどきその名前を目にすると、妙に懐かしい気持ちになる。僕と小森くんはよく『パワプロ』の対戦モードで戦った。小森くんから僕を誘ってくれた。たぶん、小森くんはゲームがへただったから、一人ではゲームを進められなかったのだと思う。小森くんは『ドラゴンクエスト』や『ファイナルファンタジー』とかのロールプレイングゲームは一人で進めていた――ときどき僕がレベル上げの手伝いをしたり、進めるのに必要な謎解きの手伝いをしたりしていた――が、『ストリートファイター』や『鉄拳』みたいな格闘ゲームはすぐに飽きて埃をかぶっていた。『パワプロ』にも、格闘ゲームのような――もちろん格闘ゲームほどではないが――動体視力や瞬発力などの、直接的に身体的な操作を求められるところがあるから、一人で遊ぶのは難しかったのではないかと僕は思う。そういうわけで、小森くんは『パワプロ』をやるときは決まって僕を誘った。僕らは野球をやったこともなければ実際の野球の試合を観たことすらもなかったが、『パワプロ』で遊ぶのは好きだった。僕らは野球というスポーツを『パワプロ』で知り、野球のルールを『パワプロ』で学んだ。僕らにとって野球という概念はゲームの中にだけ存在するものであり、それは、どこまでいってもバーチャルなものだった。そこには生身の肉体はなかった。僕にとって野球とは、生きている人間によって行われるスポーツではなかった。それは、純粋にロジックでありパラメーターでありデジタルなものの集積だった。そして僕にとってはそれでよかった。僕はいつまでもそれでよかった。僕はそんな野球だけをずっと好きでいたかった。けれど小森くんにとってはそうではなかったらしい。
その日も僕は、いつものように放課後に、小森くんの家で『パワプロ』をやって遊んでいた。小森くんはずっと読売ジャイアンツを操作し、僕はずっと中日ドラゴンズを操作していた。いまもそうかはわからないが、当時のジャイアンツはとても強く、とてもいい選手たち――レーダーチャート上に表現される、バランスのとれた能力値を持った選手たち――がたくさん在籍していたので、勝ちたければ誰だってジャイアンツを選んだ。そして小森くんはいつも勝ちたがっていたので、いつもジャイアンツを選んだ。小森くんは僕にジャイアンツを選ばせることを許容しなかった。僕はジャイアンツ以外には、地元のチームであるドラゴンズしか名前を知らなかった。だから僕はいつも中日ドラゴンズを選んだ。そして僕はそのことを不服に思っていた。それでも僕はそれを直接口に出していうことはなかった。それでも別にそれでよかった。僕らはいつも、互いに勝ったり負けたりを繰り返していた。僕らはそれを楽しんでいた。
二回か三回くらい、対戦を終えたときのことだった。次の対戦をするために、僕はコンティニューのボタンを押した。そのとき唐突に、小森くんがゲームの電源を切った。ブラウン管のテレビがぷつんと音を立て、画面の真ん中あたりに白い横線が入って、やがてゆっくりと消えていった――大人になってから知ったことだが、ブラウン管テレビの画像は、走査線と呼ばれる細かな光の線をいくつも束ねることで描画されている。もちろんそんな知識はもう、どこにいたって使うことはないのだけれど。
小森くんは隣に座る僕を見て、ちょっと思ったんだけど、というようなことを言った。僕は、何? と言いながら小森くんに顔を近づけた。
小森くんは、何かよくないことを確認するみたいに、静かな声で、ためらいがちに、「野球、やってみない?」と僕に言った。
僕は驚いた。僕は一瞬頭が真っ白になり、それから小森くんが野球をしている姿を想像しようとしたが、うまく想像することはできなかった。
「え。どういうこと」と僕は言った。
「野球。ゲームじゃなくて、ほんとのやつ」と小森くんは言った。
僕は混乱していた。
「え。よくわかんない。道具とかないし」と僕は言った。
小森くんは眉間に皺を寄せ、小さな唸り声を上げ、それから、「樋口くん、いまいくら持ってる?」と言った。小森くんは僕の目を覗き込んだ。僕も小森くんの目を覗き込んだ。小森くんの瞳は不安げに揺れていたが、冗談を言っているようには思えなかった。小森くんは笑っていなかった。小森くんは、たぶん本気だった。そのとき僕にはそう見えた。僕はたじろいでいた。
「いや、そんなないけど、小森くんは?」と僕は言った。
「僕もそんなないけど」と小森くんは言った。
僕らは財布を出し合って、互いのこづかいを畳の上に広げた。小銭がじゃらじゃらと音を立ててぶつかりあった。僕らは小銭を数えた。一円玉とか十円玉が多かったように思う。たぶんそうだったと思う。当時の僕らは百円玉を持っていたらいい感じで、五百円玉を持っていたらすごい金持ちだった。もちろん、具体的にそのとき僕らがそれぞれいくら持っていたかなんてことは覚えていない。けれど百円玉や五百円玉はそこにはなかった。いずれにせよ、とにかく本物のバットやボールやグローブを買えるほどの金額ではなかったことは覚えている。
「全然ないね」と小森くんは言った。
「おばあちゃんに買ってもらったら?」と僕が言うと、「いや、そこまでではないかな」と小森くんははっきりと言った。小森くんには珍しく、びっくりするくらい即答だったから、実際に僕はびっくりしてしまい、しばらく応答することができなかった。ちょっとした沈黙が僕らのあいだに横たわった。小森くんは続けて何かを話すかと僕は思ったが、小森くんはそれっきり何も言わなかった。当時の僕には、なぜ小森くんがそんなふうに答えたのか、当時の僕にはよくわからなかったが、いまの僕にはなんとなくわかる。それはたぶん、小森くんにとって、他の誰にも知られたくない、勘ぐられたくない、期待もされたくなければ不安にも思われたくない、僕らだけの秘密の実験だったのだ。いまの僕はそう思っている。あるいはいまの僕は、そう思い込もうとしている。小森くんは立ち上がった。僕も立ち上がった。「ダイソーに行こう」と小森くんは言った。
僕らは外に出た。僕らは自転車をこいで、近所のダイソーに行った。ダイソーは、小森くんの家から自転車で5分くらい行った先にあった。ドブ川を横目に、町工場を抜けて、大通りに出る。その先に、スーパーがありGEOがあり大船堂という名前の少し大きな書店がある。ダイソーはその一画に並んでいる。小学生の頃は、何か困ったことがあればすぐダイソーに行っていた。ジュース、菓子、誕生日会のプレゼント。なんでも売っていた。調べ学習に使えそうな本も売っていたような気がする。地理の本、歴史の本、その他まとまりのない雑多な知識を集めた本。とにかくダイソーに行けばなんでも手に入った。小学生の頃の僕にとってはそうだった。もしかしたら中学生の頃もそう思っていたかもしれない。中学生になると、不良になった友人たちはダイソーで万引きをすることで、仲間同士の結束を確認していた。ジュース、菓子、ジェルとかワックスみたいな整髪剤、どんな曲が入っているのかわからないCD、それから女の裸が描かれたDVD。僕と小森くんは、なけなしのこづかいを出し合って、プラスチックでできたバットと、ゴムでできたボールを買った。グローブの代わりになるものは売っておらず、あきらめた。けれど、僕らにとってはそれで十分だった。
僕らはダイソーを出て、ふたたび自転車を漕ぎ始めた。
僕は買ったばかりのバットとボールが入った袋を、自転車の左ハンドルにぶらさげていた。プラスチックのバットは鮮やかな蛍光グリーンで、まるで主婦の買い物袋の中のネギみたいなかっこうで、ビニール袋から突き出ていた。
「野球、どこでやる? 学校?」僕は自転車を走らせながら小森くんに訊いた。
「いや」と小森くんは言った。「学校はやめよう」
どうして? と僕は思ったが、その言葉を口に出すことはなかった。小森くんは黙ってペダルを漕いでいた。小森くんは理由を言わなかった。小森くんは理由を言う必要がなかった。僕には小森くんがそう言った理由がわかった。放課後の学校は僕らのものではなかった。放課後の学校には「スポーツをするグループ」がいて、「本物の野球」や「本物のサッカー」などの「本物のスポーツ」をして遊んでいた。僕はそのことを知っていた。小森くんもそのことを知っていた。彼らは本物で、僕らは偽物だった。放課後の学校は、本物である彼らのもので、僕らのような偽物のための場所ではなかった。僕らにはそのことがわかっていた。
「神社に行こう」と小森くんは言った。「あそこなら、たぶん大丈夫」
神社で野球なんかできるのか? と僕は訊ねたが、大丈夫、たぶん大丈夫だと小森くんは繰り返し言った。そこならひとけは少ないし、大人が来ても怒られることはないのだと小森くんは言った。小森くんは小さな頃から、その神社で遊んで育ったのだと言っていた。僕は半信半疑だったが、特にこだわりがあるわけでもなかったので、小森くんの言う通りにした。そもそもこの話は、小森くんの物語なのだ。主役は僕ではなく、僕が主体性を発揮するべきではない。僕はいま、書きながらそんなことを考え、そしてここにいる僕は、思い出の中の僕を思い出の中の小森くんに従わせる。
そうして僕らは小森くんの家の近くにある神社に向かった。神社にはすぐに到着した。神社は広く、周辺は大きな木や竹藪に囲まれ、そこだけ町から切り離されているように思えた。近くには池があり、そこでしか見れない真っ白な鳥が飛ぶのが見えた。池は深く、濁っており、底は見えなかったが、ときどき魚の影がゆらゆらと泳いでいるのが見えた。僕は見たことはなかったが、その池にはスッポンがいるのだと小森くんは言っていた。小森くんはそれを、小森くんのおばあちゃんから聞いたのだと言った。小森くんはスッポンを見たことがあるのかと訊ねると、小森くんも見たことはないのだと言った。けれど、そこにはスッポンがいるのだと、小森くんは信じていた。僕はその話を信じていたわけではないが、信じていなかったわけでもない。特に理由はないが、いたほうがいいなとは思っていた。自分の住む町に野生のスッポンがいるというのは、想像してみると面白いような気がした。いまもそう思っている。そう思いながら、この文章を書いている。
神社に到着すると、僕らは自転車を鳥居の前にとめ、ボールとバットをダイソーの袋から取り出した。僕は偽物のボールを、小森くんは偽物のバットを持って、境内に向かって歩き出した。
鳥居をくぐると、数メートル先に石段があった。石段はそれほど大きくはない。数段のぼるとその先に賽銭箱が置いてあり、賽銭箱の奥は建物になっている。扉は閉まっており、中は見えない。
小森くんは小走りに駆け、先に石段の前に到着すると、足元に並ぶ石畳の一つをバッターボックスに見立て、本物のバッターのようにバットを握り直し、僕に向かってかまえた。
「ちょっとそこから投げてみてよ」と小森くんは言った。僕はボールを投げた。僕は自分なりに本気で投げた。ボールは思ったよりもずっと速く、前に向かって飛んでいった。小森くんはバットを振ったが、全然違う場所で空を切っていた。ボールは石段にぶつかって、バウンドしながら僕のところに返ってきた。僕はそれをとろうとしたが、うまくとることはできなかった。ボールは鳥居を超えて、道路に出たところで止まった。僕は走ってボールを追いかけた。
「すごい」と小森くんは言った。「もう一回やろう」
そうして僕らは偽物の野球を始めた。ポジションはピッチャーとバッターだけ。出塁はない。バットがボールに当たり、ピッチャー役がそのボールを取れなかったらヒットとして扱う。ヒットが3つ重なると1点。鳥居を超える大きな当たりをホームランとして扱い、1点として数える。ストライクかボールかはそのつど二人の主観をすり合わせて判定する。ボールが4つで1ヒット、ストライクが3つで1アウト。3アウトでチェンジ。それが僕らの作った即席のルールだった。僕はボールを投げた。小森くんはバットを振った。小森くんはボールを投げた。僕はバットを振った。僕はボールをキャッチしたりキャッチしなかったりした。小森くんはボールをキャッチしたりキャッチしなかったりした。何度もそれを繰り返した。最初はうまくできなかったが、繰り返すうちにバットはボールに当たるようになり、飛んできたボールをキャッチできるようになっていった。僕らは少しずつ、自分たちが本物の野球をやっているような気分になっていった。小森くんがどうだったかはわからないが、少なくとも僕はそうだった。僕は『パワプロ』の中で動き回る、バーチャルなプロ野球選手たちと自分を重ね合わせていた。ボールが石段にぶつかって、弾けるような音を立てるたび、バットがボールをとらえるたび、空高く舞い上がり落ちてくるボールを手のひらで受け止めるたび、僕は自分が「スポーツをするグループ」のメンバーになったような気がした。あるいは自分が本当に、明日からでも「スポーツをするグループ」の中に入れるかもしれないと思うと、視界が果てしなく広がっていくような心地を覚えた。僕はそれまでに、自分にそんな可能性があるとは考えたことがなかったし、それに限らず、自分に何かの可能性があるとは考えたことがなかった。それは一つの発見だった。それとも発明だった。世界が自分の前に開かれていることの発見。世界が自分の前に開かれていると思うことの発明。そのときいだいたそういう感覚を、僕はいまもはっきりと覚えている。僕はなんでもできる。少なくともそう思うことはできる。そしてそう思うことは楽しい。たとえ本当はそうではなく、本当は何もできなかったとしても、力がみなぎってくるような気がすることならできる。

夕方は終わろうとしていた。少しずつあたりは暗くなってきていた。車が何台か通り過ぎ、ヘッドライトが路上に光の線を描いた。上空から、群れをなして飛ぶカラスたちが鳴くのが聞こえてきた。でも僕らは僕らの野球をやめなかった。僕はやめることを言い出さなかった。小森くんもやめることを言い出さなかった。ボールは少しずつ見えにくくなってきていたが、まったく見えないわけではなかった。夜が来ればきっと、小森くんのおばあちゃんは小森くんを探しに来るだろう。けれど今はまだその時間じゃない。夜はまだ来ていない。僕らはまだ、僕らの時間を続けることができる。誰かに止められるまで、僕らは僕らの野球を続けるつもりだった。
小森くんはボールを投げ、僕はバットを振った。バットはボールに当たらなかった。小森くんは、石段に当たって跳ね返るボールを受け止めた。小森くんの投球フォームはそれほどさまになっているわけではなかったが、速度は上がっていたし、コントロールもよくなっていた。跳ね返るボールを何度もトンネルさせながら、いまではなんとか、両手を使ってキャッチできるようになっていた。
2アウト、2ストライク。小森くんは、最後のストライクをとるために、ボールを何度も握り直し、首や肩を回して疲れた筋肉をほぐしていた。小森くんはフォームを作り、腕を振りかぶった。
そのとき、遠くのほうから大きな笑い声が聞こえた。僕も小森くんも、声のするほうを見た。僕は他人の笑い声が嫌いだった。他人の笑い声を聞くと、なぜか心がざわつき、不安な気分になった。声がしてからすぐに、自転車に乗った子供たちが神社の前を通り過ぎていった。僕らくらいの年齢だ。よく見ると、クラスの「スポーツをするグループ」だとわかった。彼らは自転車のカゴの中にグローブをつっこみ、背中にはバットを入れるケースを背負っていた。彼らは一度視界から消え、それから旋回して戻ってきた。鳥居の前に自転車をとめると、僕らを指差しながらこっちに向かって歩いてきた。「小森と樋口じゃん」と誰かが言うのが聞こえた。本当はそんなことはなかったのかもしれないが、僕には聞こえた気がした。「お前ら、こんなとこで何してんの?」
「スポーツをするグループ」は、全員自転車から降り、鳥居をくぐって、次々と境内へと入っていった。山田くん、後藤くん、大島くん、安藤くん、田中くん――普段はほとんど交流することがないから、彼らの外見をちゃんと見るのはそのときが初めてだった。全員、スポーツ刈りで、野球のキャップをかぶっていて、肌が日に焼けて黒く、筋肉で腕や胸が盛り上がっている。長い前髪が目にかかり、肌の色が白く、細くてTシャツの袖がぶかぶかの僕らとは対照的だ。彼らはこっちに向かってゆっくり歩いてきた。
「何あれ?」
「おもちゃのバットじゃね?」
「あいつらいつもあんなんで遊んでんの? マジウケるんだけど」
「幼稚園児かな?」
「いや俺幼稚園行ってたときからバット持ってたけど」
「つーかあいつらは保育園卒じゃね? 略してホイ卒」
「いや、それはどっちでもいいわ」
彼らが口々にそんなことを言うのが聞こえた。顔が熱くなり、汗が噴き出すのを感じた。目の中で光がちかちかと瞬き、眩しかった。自分の体が縮こまり、消えてなくなってしまいそうな気がした。あるいはすぐにでもその場から消えてしまいたかった。
「お前ら、もしかして野球やってんの? こんなところで、二人で?」と山田くんが言った。僕はなんと答えればいいかわからなかった。僕は混乱していた。自分がやっている遊びが野球だとは思わなかったが、それまでは野球をやっているつもりでその遊びを遊んでいた。それをなんと呼べばいいのか僕にはわからなかった。その遊びを示す言葉を、僕はうまく見つけることができなかった。僕は黙っていた。
僕が黙ったままでいると、 「うん、そうだよ」と小森くんが言った。
僕は小森くんの顔を見た。小森くんの唇は少し震えていた。他のやつらはくすくす笑っていた。
「へえ。それちょっと貸してくれよ」と山田くんが言った。山田くんは僕が握っていた蛍光グリーンのプラスチックバットを指さしていた。僕は山田くんにバットを渡した。山田くんがそのバットを握ると、バットはまったくのおもちゃのように――実際それはおもちゃにすぎなかったのだが――、安っぽく貧相なものに見えた。僕らくらいの年齢の男子がそのバットで遊ぶということが、ひどく滑稽なことだということがわかった。僕は恥ずかしくなり、バットから目をそむけた。小森くんのほうを見ると、後藤くんが小森くんの手からゴムボールを剥ぎ取っていた。「なんだこれ、ぷにぷにのゴムボールじゃん」と後藤くんは言った。「逆にこんなん投げるほうがむずいだろ」
「おい、言い訳やめろ。ピッチャーだろ」山田くんがにやにや笑いながら言った。山田くんはプラスチックバットで素振りを始めていた。山田くんのバッティングフォームはとてもきれいだった。小森くんや僕は偽物にすぎなかったのだと思った。
「ちょっと軽く投げてみるわ」と後藤くんが言った。後藤くんはゆっくり歩き始め、僕らから距離をとった。後藤くんが止まった場所は、僕らがボールを投げていた場所よりもずっと遠い場所だった。そんなところからボールを投げて、ノーバウンドで石段に当てることは、僕や小森くんにはできないだろう。後藤くんはマウンドに立つみたいに足を踏み鳴らし、それから仁王立ちをした。後藤くんはボールを見つめながら適切な握り方を確認した。山田くんはバットを立てて、後藤くんのボールを迎え撃つ準備をした。後藤くんは山田くんのほうを見た。山田くんも後藤くんのほうを見ていた。二人は黙って見つめ合っていた。神社が静寂に包まれた。風が吹き、木の葉が擦れ合う音だけが聞こえていた。
後藤くんが振りかぶった。後藤くんがゴムボールを投げた。ボールが後藤くんの手から離れたその瞬間、ボールが空中で消えた。山田くんはバットをフルスイングで振り抜いた。風船が弾け飛ぶような音がして、ふたたびボールが現れた。気づくとボールは空高く飛んでいた。それは一秒にも満たない短い時間のできごとだった。何が起こったのか、僕にはまったくわからなかった。思考が事態に追いついたときには、すべてはとうに終わったあとだった。ボールはきれいな弧を描き、遠くのほうにある、竹藪の中へと消えていった。その先にはスッポンが住んでいるという池があった。
「あーあ」と後藤くんが言った。「どっか行っちゃったじゃん。どうすんだよ」
「はあ? なんだよ、俺が悪いのかよ」と山田くんは言った。「こんなもん、別にどうなったっていいだろうがよ。ガキじゃねえんだから」
山田くんはプラスチックのバットを持ち直し、それから腕を横に広げてバットの両端を握りしめると、そのまま真ん中で折り曲げた。バットはなすすべなく、なんの抵抗もなく、一瞬で、水飴みたいにぐにゃっと曲がった。おいおい、やめてやれよ、と後藤くんが言って笑った。ほかのやつらも笑っていた。山田くんは折れ曲がって半分の長さになったバットを僕に渡すと、「じゃあな」と言った。それから山田くんたち「スポーツをするグループ」は、神社の外に向かって歩き始め、自転車に乗って去っていった。笑い声が遠ざかり、やがて闇の中へと消えていった。後には僕と小森くんと、折れ曲がった、バカみたいな色をしたプラスチックのバットだけが残された。僕らは何も話さなかった。何も話そうとしなかった。僕はその場に立ち尽くしたままで、小森くんもそこに立ち尽くしたままだった。風が強くなってきていた。夜が近づいてきていた。カラスの鳴き声ももう聞こえなくなっていた。
そのとき僕は泣きたくなるような気分だったし、泣いてもいいような気がしたが、けれども僕は泣かなかった。小森くんのほうを見ると、顔を赤らめて何かに耐えているような感じだったが、小森くんも泣いてはいなかった。僕らの野球は終わったが、それでいいような気もした。むしろ、そうあるべきだとすら思った。すべては終わるべきことのように思えた。あるいは僕はそう思い込もうとしていた。そしていまの僕もそう思い込んでいる。それから僕は、野球をやることも、野球のまねごとをやるようなこともしていない。
小森くんは黙ったままで歩き出し、スッポンが住んでいるという池に向かった。
小森くんは竹藪の中に座り込み、草をかきわけながらボールを探した。僕は、もう探さなくてもいいんじゃないか、と思ったが、それを口に出すことはなかった。僕も小森くんと同じように、その場に座って草や土を触りながらボールを探し始めた。もっと正確に言えば、僕は探すふりをし始めた。僕は、そのとき自分が何をすればいいのか、自分が何をするべきなのかはわからなかったが、そうしないよりはそうしたほうがマシなように考えた。僕は、もうボールは見つからないと思っていた。そして実際に、ボールは見つからなかった。僕は何か別のものを探していた。あるいは何も探してなどいなかった。中学生になると、僕は小森くんとは遊ばなくなった。理由は明白だ。思春期になって、僕はそれまでの僕ではなくなってしまった。13歳になった僕は、自分がいかにも偽物らしい偽物であることに耐えられず、本物に見えるように振る舞う偽物になった。小森くんはずっと、偽物らしい偽物のままだった。というかそもそも小森くんの世界には、本物とか偽物とか、そういう区分がなかったのだと思う。そしてそれは、山田くんにしたって後藤くんにしたって同じことだ。世界を本物とか偽物とかいう区分で見ているのは、たぶん、偽物である僕だけだ。
竹藪の中に入るのはそのときが初めてだった。池を間近で見るのはそのときが初めてだった。僕は池の中を覗き込んだ。僕は目をこらした。暗闇の中、ところどころに波が立っていた。それが風によるものなのか、池の中に潜む魚たちによるものなのかはわからなかった。池の周りにはコオロギやバッタがたくさん跳びはねていた。池の中に、本当にスッポンが住んでいたかどうかは、そのときもわからなかった。それはもちろんいまもわからない。そして、今後もわかることはないと思う。