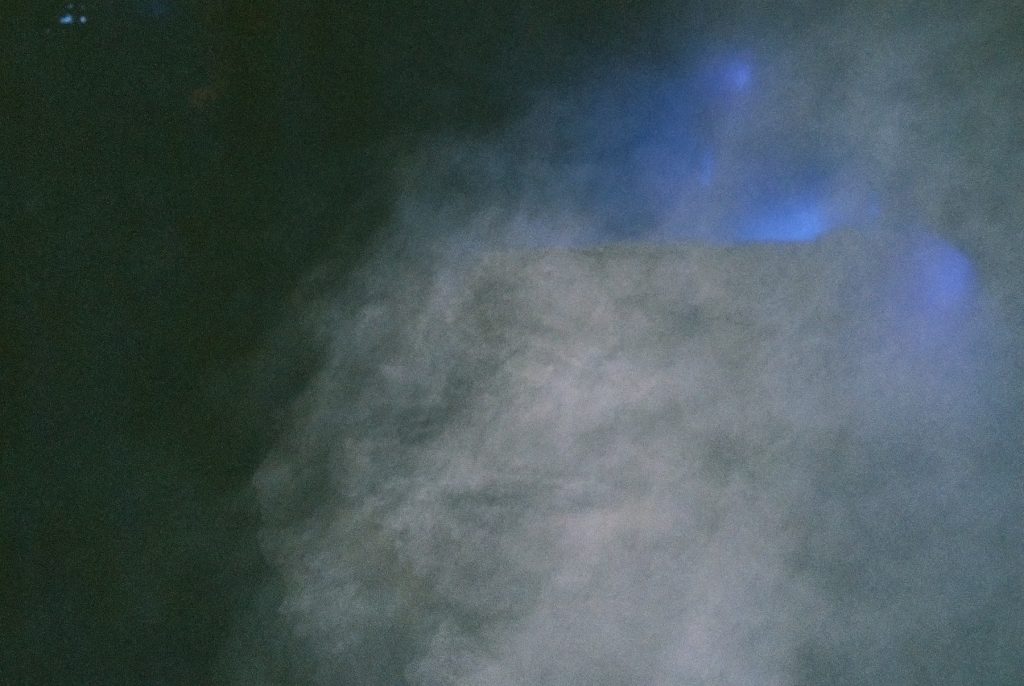今朝、目が覚めて、意味のないことを書こうと思った。
理由は特にない。ただ、書きたくなったから書こうと思った。こういうことがときどきある。そして、文章というのは本来、そういうものであり、そうあるべきだとも思うので、僕はこういう欲望にあらがうことをしない。
僕はこれから意味のないことを書き始める。
意味のないことは、意味のないことなので、特に何も考えずに書き始めることにする。
誰にも共有できない記憶というものがある。
誰かと共有可能な記憶というものは、誰かにとって役に立ったり、役に立つことはなくとも、聞いていて面白かったり、理由はわからなくとも惹かれるところがあるものだ。どんなに瑣末なできごとであれ、どんなに私的なものであれ、それは、語り手以外の誰かに向けて、誰かのために、誰かの効用に寄与するべくして語られる。
誰にも共有できない記憶というものは、そのような、共有可能な記憶以外のすべての記憶を指している。
語られるものは、語られるべくして語られる。
語られないものは、多くの場合、永遠に語られることはない。
語られないものとして語られるものは、語られないものとして語られることはない。
僕がこれから試みようとするこの文章もまた、そのような、あらかじめ定められた失敗に向かって書かれ、書かれることはないだろう。

高校生のとき、工場でバイトをすることになった。スーパーやコンビニに並ぶ食品や飲料の在庫を保管している工場だった。食品や飲料はでかいダンボールの中に入っていた。それらのダンボールを、ある区画から別の区画に運ぶのが、僕の作業ということになっていた。その作業にどんな意味があるのかは当時はよくわからなかったし、今もよくわからないが、とりあえず、僕はダンボールを運んでいた。
どうしてバイトをしなければならなくなったかというと、家の電話で長電話をしすぎたからだ。週末になると、当時付き合っていた彼女に電話をかけた。電話は夜に始まって、朝に終わった。何を話していたのかは覚えていない。最近聴いた音楽や観た映画のことを話していたような気がする。そう言えば、ビョークの話をしたな。僕はビョークが好きだった。彼女もビョークが好きだった。本当は彼女はそうではなかったかもしれないが、僕の記憶の中ではそういうことになっている。彼女が何を話していたかはまったく覚えていない。僕は人から言われたことをほとんど覚えていない。僕は人の話を全然聞いていないのだと思う。僕はいつも、一方的に話している。僕しか話していない飲み会みたいなのがかなりよくある。それはよくない癖だと思う。それから八年くらい経って、会社員になると、僕は上司に怒られることになる。自分から話しすぎるな、人の話を聞け、と上司は言った。僕はそれを聞いて、たしかに、と思った。そしてそれを実際に行動に移した。僕は自分から話さなくなった。それで僕は、大学を卒業して最初の三年くらいは、うまく話すことができなかった。
話が変わってしまった。
文章を書いていると、すぐに話が変わっていく。
僕はそれがおもしろいことだと思う。
そうそう。それで、僕が長電話をしすぎて家の電話代がかさみ、家の電話代を僕が払うことになったんだった。
田舎の高校生がバイトを見つけるのは大変だ。しかも僕は世間知らずだった。バイトの受かり方を知らなかった。まあ今でもよく知らないが。たしか最初は近所のバーミヤンとかミニストップのバイトを受けたんだったんじゃないかな。店頭にバイト募集の貼り紙がしてあったから。貼り紙に書かれた電話番号をメモして、家に帰って、さっきのメモを取り出して、その電話番号に電話をかけて、電話がつながった。大人の声がした。大人の声がした、というのはもちろん嘘で、そんな記憶は残っていない。物語的に、普通に考えたらそうなるというだけだ。これは基本的にはフィクションではないが、物を語っているのだから物語であるには違いない。物語には物語の論理がある。物を語っているときの僕の記憶は、物語の論理にたえず揺さぶられ続けている。そのころの僕は、親と先生以外の大人と会話したことはなかったから、緊張していた気がする。たぶん緊張していたんだろう。よく思い出せない。面接の場所と日時を指定されて、履歴書を書いて持っていった。僕は履歴書というものがそもそもなんなのか知らなかったが、親に聞いたら教えてくれた。母親がパートの面接を受けた余りが家にあったのでそれを使った。もちろんそんな記憶もない。母親がパートをしていたのは事実だが、「母親のパート」と「履歴書」という二つの記号を、それらしくつなぎ合わせてみただけだ。僕はこういう、どうでもいい、しょうもない、小さな嘘をよくつく。虚言癖かもしれないな。たぶんきっとそうなんだろう。ところで僕のつく嘘はしょうもないし、全然練り上げられておらず、すぐバレるようなものなので、親しい人々にはもう、僕がそういうやつであることはバレている。特に妻は、僕の最も親しい人であるために、日常茶飯事のように嘘がバレては笑われる。ところで、そういう嘘は、小説の中では許されるので、小説は優しいものだと思う。履歴書には証明写真を貼る箇所があったが、聞くと証明写真を撮るには金が必要だということだった。五〇〇円とか、そのくらいの。当時の僕には金がなかったので、証明写真を撮らずに、空欄のままで履歴書を持っていった。まあしかし、金があっても証明写真を撮っていたかどうかは怪しい。五〇〇円あれば、近所のGEOで中古のアルバムが買えるかもしれない。あるいは近所のパイナップルというTSUTAYAのパチモンみたいなレンタルビデオ屋で映画が二本借りられる。写真なんかに金を使うより、どう考えてもそっちに金を使うほうが有意義だろう。当時の僕はそう考えていた。そう考えていたに違いない。あるいは今の僕はそう考えている。パイナップルは、僕にとってはとても思い出深い場所で、実家に帰るたびに行ってしまうが、2010年くらいに潰れてなくなっていた。バッティングセンターになっていた。
で、面接は落ちた。バイトの面接って落ちるんだ、とそのときは思ったが、大学生になって東京でバイトを探していたときも、バンバン落ちていたので、まあ、僕はそういう人間なんだろうと思う。大学一年のときに、高田馬場にある、全国チェーンの某服屋(別に僕は固有名詞を出してもいいんだけど、もしかしたら迷惑がかかるかもしれないので控えよう)でバイトをしたことがあるが、そこの店長がマジでめちゃくちゃいい人で、バイトのみんなで飲みに行ったとき、「きみは世間知らず過ぎて、この先の人生ちゃんと生きていけるか心配だったから、勉強させてあげたいと思って採った」みたいなことを言っていた。なんかこの書き方だと嫌味っぽい気がするが、そういうことではまったくなかった。まあ、店長の意図とは裏腹に、僕はそのバイトを辞めたあとにも、まったく世間知らずのまま人生を歩んでいくことになるのだが。服屋のバイトは、なんで辞めたのか思い出せないな。いい職場だったのに。辞めるときに、送別会を開いてもらった記憶がある。そのとき僕の直接の先輩だった契約社員の人に、こんなことを言われたのを覚えている。「お前は俺たちのことをバカにしてる。顔ではみんなに合わせて笑ってるけど、腹の底では違うだろ。自分ではうまく隠せてると思ってるかもしれないけど、みんな気づいてるよ。明日からお前ともう会えないと思うと、正直言ってほっとするよ。みんな、お前のことが好きじゃなかったんだ」
いや、何の話してたっけ。

工場の話だ。そのバイトはタウンワークで見つけた。時給はたしか700円くらいだった。高校生でも働けて、実際高校生も働いていると書いてあった。その工場は実家の最寄り駅から二駅くらい先にあった。電話をすると、もう採用するから、働ける日に履歴書と印鑑だけ持ってきてほしいと言われた。もうすぐ夏休みが始まるから、夏休みの初日の昼頃に行きたいと言うと、それでいいよ、と言われた。正確にはそんな会話はしていないが、おそらくそんな感じの会話だったには違いない。共有できない記憶というものがあり、共有できない記憶は、記憶の持ち主にすら共有されていない。記憶は存在する。たとえそれが現実には起こらなかったことだとしても、あらゆる思い出は実在する。だがそれは誰にも触れられない。記憶はただそれのみで存在する。それは誰のものでもない。
工場には、金がないので自転車で行った。僕は地図を読むのが苦手で、よく道に迷う。けれど、そのときは余裕だった。線路沿いに、二つ先の駅に向かってペダルを漕ぐだけでよかった。二つ先の駅は自転車で15分くらいで行けた。暑い日だったが、不快ではない。記憶の中では不快ではない。線路と道路の間では、剥き出しの、錆びて赤茶けた鉄柵が続いていた。柵の隙間を縫うようにして、ススキに似た雑草がぼうぼうと生えていて、風に揺れていた。それは本当にススキだったかもしれない。そんなことはどちらでもいい。そこは住宅街で、プール帰りの小学生たちが手をつなぎ、列を作って歩いていた。僕は音楽を聴いていた。本当に音楽を聴いていたかどうかはわからないが、たぶん聴いていた。当時の僕は自転車に乗って音楽を聴くのが好きだった。高校までは、岐阜駅から自転車で20分くらいかかったが、僕はその道程が好きだった。週末に、友人たち四人くらいで、岐阜から名古屋まで自転車で行ったことがあった。中古のCDを買い漁るためだった。嘘かもしれない。そういう思い出があったことにしているだけかもしれない。美しい思い出がたくさんある。そのうちのどれだけが本当にあったことで、どれだけが本当はなかったことなのか、今の僕にはよくわからない。
高三のとき、友達の家に泊まって、うまく眠れず、外から漏れてくる光を使って、三島由紀夫の文庫本を読んでいたことがある。僕はそのことをすっかり忘れていたのだが、社会人になってからの酒の場で、そういう思い出話をされたことがある。「明け方に目が覚めたら、樋口はもう起きてて、何か本を読んでいたんだよ。訊いたら、三島由紀夫だって言ってて、こいつはやっぱやべえやつだと思ったね」と彼は言った。そう言われてみると、そういうこともあった気がするので、そういうことにしている。僕はその話を否定も肯定もせず、その場では曖昧に笑って応えた。その後はそのできごとについて自分でも話すようになった。そうしているうちに、実際そのときの映像が頭の中に浮かび上がるようになった。それは最初から自覚されていた思い出のように、僕が経験した美しい思い出の一つになっているのだが、その記憶は誰の記憶と言ってよいのか、僕にはよくわからない。そのできごとが事実かどうかは定かではないが、僕の中ではすっかり事実だということになっており、また、今の自分を構成する、かけがえのない思い出ということになっているために、僕はこれから、その思い出を改変することはないだろう。僕は三島由紀夫など読んだ記憶がないし、まったく影響など受けていないどころか、そこに何が書いてあるかもよく知らないし、これからも読むことはないだろうが、僕は三島由紀夫を読んだということになっている。この文章の形式と内容から言えば、たとえばアゴタ・クリストフ『文盲』などのほうが適切な気がするので、ただ単に意味のある文章を書きたいときには、僕は躊躇なく、僕の美しい思い出を差し替えることだろう。
しかし、ここにあるのは虚構ではない。ここにあるのは事実である。僕は可能な限り、ここにある事実を事実のとおり、あるがままに記そうと試みている。もちろん、ここで事実と呼んでいるものの中には、書きながら想起される、きわめて主観的な感覚も含まれる。
そのとき一緒に遊んだ友達の一人は、堀江貴大という人で、今は映画監督をしている。彼は2015年にデビューした。2016年に、名古屋のミニシアターで彼の作品の上映会があった。僕は2015年から名古屋に住んでいた。2007年から2015年の途中までは東京に住んでいて、高校時代の友達とはあまり会っていなかった。堀江貴大(以下堀ちゃん)とも高校卒業以来会っていなかった。せっかく名古屋にいるのだしと思って、久しぶりに堀ちゃんに会いに行った。堀ちゃんが撮った映画のできは、ぶっちゃけよくわからなかったが、上映会のあとで、堀ちゃんや、映画の関係者のみんなで飲みに行ったのは楽しかった。映画の話とか、音楽の話とか、小説の話とかをした気がする。そのときも僕がいろいろ一方的にベラベラとしゃべりまくった。堀ちゃんは僕の意見が鋭いと言って褒めた。僕はそれをうれしく思ったが、同時にそれを恥ずかしく思った。堀ちゃんは何かを創り、それについてはベラベラとしゃべらず、自分は何も創らずにベラベラとしゃべっているだけで、それは何か違うんじゃないかと思った。堀ちゃんは何かをしていると思った。自分は何もしていないと思った。このままベラベラしゃべるだけの人生を送るのか? 俺は、と思った。やばいと思った。それで、その翌日から僕は小説を書き始めた。
2021年現在、僕は一応小説家ということになっている。でも、小説というものがなんなのか、今も僕にはよくわかっていない。今でも、僕の中にある「自分は何も創らずにベラベラとしゃべっているだけ」という感覚には、拭い去れないところがある。この文章だってそうだろう。僕にとって小説とは、単にフィクションであるということだけを意味するわけではない。小説と呼びうる小説には、ここではない世界、もう一つの世界がなければならない、と思う。そこには、その小説の中にしかない世界の構造、世界の論理、世界の法則があって、それらが完璧に構築されていなければならない。このように、しゃべるようにしてだらだらと書かれた文章は、決して小説ではない。それを決して小説と呼んではならない。けれどこれはエッセイでもない。なぜならここにある記述の多くは、フィクション以外のなにものでもないのだから。
この文章は、小説でなければエッセイでもない。
それではこれは、一体なんなのか。
俺は一体、何をしているのか。
まあしかし、特に答えが知りたいわけでもない。
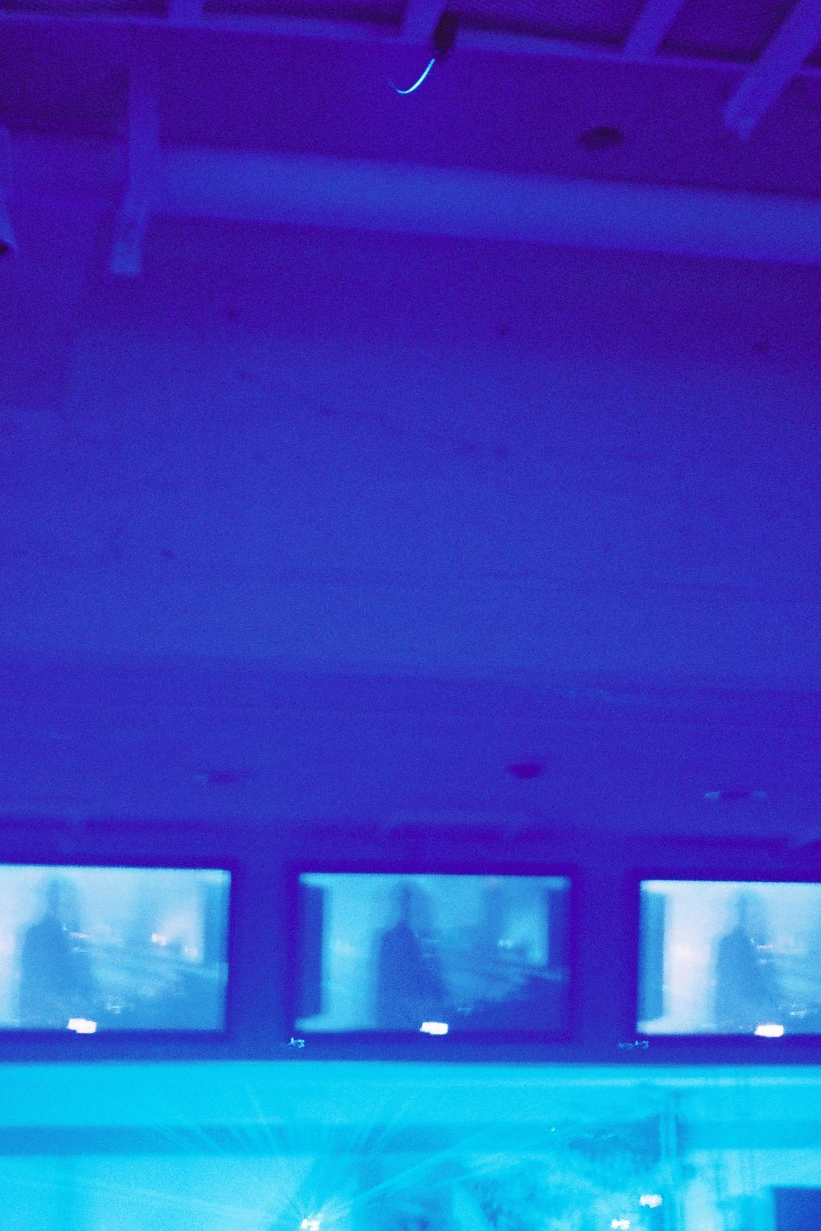
全然工場の話に戻れない。工場の話に戻りたい。
工場は最寄り駅のすぐ近くにあった。駅からもう見えていた。アスファルトで舗装された広々とした空間で、何台かのトラックが行き交うのが見えた。奥のほうに工場らしき建物があった。工場の出入口のあたりで、それをなんと呼べばいいのかわからないが、ダンボールを運ぶ、専用の、アームのついた、オレンジ色をした、小さな車もちょろちょろと走っていた。
面接のために指定された部屋は二階にあった。部屋の前にアイスクリームの自販機があった。僕は汗だくになっている自分に気づいた。アイスを買った。部屋に入った。どうやって入ったのか覚えていない。僕はまったくの部外者だったが部屋の中に入ることができた。セキュリティとかどうなっていたんだろう。部屋には誰もいなかったが、クーラーが効いていて涼しかった。僕はさっき買ったアイスを食べながら、人が来るのを待った。英語で書かれた杉原千畝の伝記のようなものを読んだ。それは100ページもないような薄い冊子だった。それを200wordかそこらで要約するのが、夏休みの英語の宿題だった。杉原千畝が誰なのかは知らなかったし、今もよくは知らないが、とにかく大事そうなエピソードを赤ペンで囲み、付箋を貼りながら読んだことを覚えている。
そうしているうちに人がやってきた。背の高い男だった。声が大きい男だった。少し崩れたリーゼントのような髪型をしていた。茶色っぽいグラデーションの入ったメガネをしていた。前歯が欠けていた。肌着の上から作業着を着ていた。首にタオルを巻いていて、タオルの先を肌着の中に突っ込んでいた。汗をかいていた。男が僕の前に座ると、少し汗臭い感じがした。それから僕らは何かを話したが、何を話したかは覚えていない。男は工場長だった。その情報をいつ知ったのかはわからなかったが、たぶんそのときだろう。工場長はペットボトルで何かを飲んでいた。僕は写真の貼られていない履歴書を見せた。工場長は履歴書を受け取ると、そのまま折りたたんでポケットにしまった。工場長は仕事の内容について説明した。僕は仕事の説明を聞いた。その日から、僕は工場で働くことになった。僕は工場長はと二人で工場まで降りてゆき、ロッカールームに荷物を置いた。タイムカードを切って、軍手をはめた。工場長に、これから僕の担当になるという区画まで連れて行かれた。そこにはペットボトルの入ったダンボールが山のように積まれていた。とりあえず、これを全部外のトラックまで運んだら教えてほしい、と工場長は言って、どこかへ消えていった。
なんだか書いてておもしろくなくなってきた。
そもそもなんで、僕はこんな話をし始めてしまったのだろう。
わからない。書き始めたときと、書いているときと、書き終えるときの、それぞれの自分は、それぞれ全然違う人間のように思える。書き始めるときは書き始めるときの気持ちしかわからない。書いているときは書いているときの気持ちしかわからない。書き終えるときは、書き終えるときの気持ちしかわからない。僕には僕がわからない。僕には瞬間しかないと思う。
だから、唐突ながら、この文章はもう終わりにしよう。
バイトは夏休みの初日に始まって、夏休みの途中で、行くのがめんどうになって、そのまま辞めた。
工場では、楽しそうに働いている人もたくさんいたが、僕はそうではなかった。職場が悪いわけではなかった。仲良くなった人もいた。髪の長いフリーター、名前は忘れてしまったが、美容学校を出たばかりのその男は、こんなに楽な仕事はないよ、と言った。他のバイトはもっと大変。ここの仕事は力仕事だけど、自分のペースでできるし、働く時間も自分で決められるからね。こんないいバイトは初めてやったな、とフリーターの男は言った。僕は、そうなのか、と思って、これからの人生に恐怖を覚えた。一生こんなことが続くのなら、人の人生ってなんなのだろう、と僕は思った。ダンボールを持って歩きまわっているあいだ、時間が流れるのがとても遅く感じた。マジで無駄な時間だなと思った。僕は落ち着きのない人間だった。僕は反抗的な人間だった。僕はパンクロックが好きだった。僕はバイトが嫌いだった。今も労働は基本的に嫌いである。しかし世の中にはそうでない人も多くいる。反抗的な文化や思想に触れた人間が労働に適応できないのか、労働に適応できない人間が反抗的な文化や思想を好むのかはよくわからないが、これまでに、仕事を楽しそうにこなす人と話が合ったためしはない。それは今現在もそうである。僕は学校という場所は好きだった。僕にとってそこは遊び場だった。勉強は遊びのようなものだった。子供にとっての義務が勉強で、大人にとっての義務が労働ならば、大人になっても今のような状況が続くのだろう、と子供のころは思っていた。けれど、どうやらそうではないらしい、ということを、僕はバイトをすることで初めて知った。その現実は受け入れがたいものがあった。そして僕は今も、その現実を受け入れられていない。僕は今もどこかで、遊ぶように労働をし、自由な心のままに生きていける方法があるのだろう、と思っている。それは甘い考えかもしれないし、実際他人からそう指摘されたこともあるが、考えが甘いからと言って、だからどうしたと言うのだろう。誰がなんと言おうと、あるいは僕自身がどう思おうと、甘い考えを持ったまま、甘い考えを持った自分を引き受けたままで、僕は生きていくしかないのだ。
高校を卒業してからというもの、労働をしていない期間はおそらくないが、それは自ら進んでそうしたわけではない。労働が自由なものではないということ、あるいはそもそも労働をしない自由が剥奪されているというのは、本当におかしなことだと思う。僕らは自由であるべきだ。僕らは楽して、楽しんで生きるべきだ。誰にもその自由を、楽しさを奪われるべきではない。
奇妙な文章になってしまった。僕は奇妙な文章ばかり書いている。
工場のバイトでは大体4万円くらい稼いだと思う。その金は、ちゃんと親に渡したのかどうか覚えていない。夏休みの終わりは、パイナップル(近所にあるTSUTAYAのパクリみたいなレンタルビデオ屋)でVHSをたくさん借りて、一人で映画を観ながら過ごした。